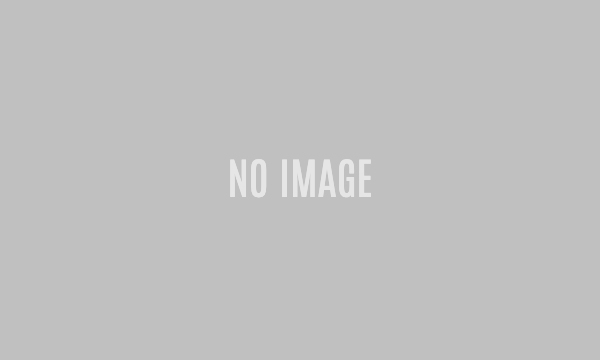「稲荷神社に行ってはいけない人はどんな人?」「稲荷神社が怖いと感じるのはなぜ?」と疑問に思っている人は多いのではないでしょうか。
この記事では、稲荷神社に行ってはいけない人の特徴や怖いと感じる理由、そして歓迎されていないサインについて詳しく解説していきます。
また、稲荷神社の参拝で気を付けることについても触れていきますので、これから稲荷神社へ訪れる予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
稲荷神社とは?

まずは、稲荷神社とはどのような神社でどんな神様が祀っているのか、また、どのようなご利益があるのかを具体的に解説していきます。
そもそも稲荷神社とは?神道系列と仏教系列って?
稲荷神社は、稲や穀物などといった「稲」に関わる神様を祀っています。
赤い鳥居を構え、境内には狛狐があることで知られており、日本には約3万社以上存在していると言われています。
また、全国にある全ての稲荷神社の総本社が京都の伏見稲荷大社です。
稲荷神社には「神道系列」と「仏教系列」の二つの系統があり、祀られている神様が異なります。
それぞれの特徴は下記のとおりです。
| 神道系列の特徴 | 仏教系列の特徴 |
|---|---|
| ・神道系列は神社である(名称は〇〇稲荷神社とつくことが多い) ・お祀りしている主な神様は「宇迦之御魂神(うかのみたまかみ)」 ・総本社は京都の伏見稲荷大社 | ・仏教系列は寺である(名称は〇〇稲荷となっていることが多い) ・お祀りしている主な神様は「荼枳尼天(だきにてん)」 ・中心となるお寺は愛知県の豊川稲荷 |
神道系列と仏教系列はどちらも食べ物にまつわる神様が祀られています。
名称や祀られている神様が異なるので、確認するとすぐに見分けられますよ。
稲荷神社は狐と関係がある?
稲荷神社といえば狐をイメージする人が多いと思いますが、狐は神様ではなく「眷属」と呼ばれる神様の使いとして祀られているんです。
狐が神様の使いになった理由として以下の点が挙げられます。
- 狐は実った稲を荒らしてしまうネズミを捕獲してくれるため、稲の守り神とされた
- 昔から日本では狼を神の使いとしていたが、稲作の定着と共に里に住む狐が神の使いとなった
- 稲のような食物のご利益を与えてくれる「御饌津神(みけつがみ)」が変化し「三狐神(みけつがみ)」になった
- 宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)の使いが狐だった
このように、狐はさまざまな理由から神様の使いになったことがわかります。
稲荷神社のご利益は?
稲荷神社で得られるご利益は以下の通りです。
- 五穀豊穣
- 商売繫盛
- 縁結び
- 厄除け
- 学業成就
- 家内安全
- 交通安全
稲荷神社には食べ物にまつわる神様が祀られていることから、五穀豊穣のご利益が得られることが広く知られています。
しかし、これまでの歴史の中で商業の発展と共に商売繫盛の神様としても崇められるようになり、現在では生活全般にもご利益があると信仰されるようになりました。
稲荷神社が怖いと言われるのはなぜ?
稲荷神社は歴史が古く多くの人に親しまれていますが、怖いイメージを持たれている方もいるのではないでしょうか?
怖いと言われるのはいくつか理由があります。
- 祟りがあるという言い伝えがある
- 狐の眷属が動物霊であるから
- 一度稲荷神社でお参りすると一生お参りしないといけない
稲荷神社が怖いと言われるのは、祟りや狐の眷属が動物霊であるのが関係しているようです。
また「一度お参りすると辞めることが出来ない」といった言い伝えもあります。
これはあくまでも言い伝えですが、遊び半分で行ったり私欲だけの為にいくのは避けた方がいいでしょう。
稲荷神社は気持ちを込めて参拝する方にはご利益を授けてくれますよ。
稲荷神社に行ってはいけない人の特徴!歓迎されてないサインとは?

稲荷神社で参拝するにあたって、行っては行けない人や避けた方がいい状況があります。
もし心当たりがあるなら、行くことを控えた方がいいでしょう。
稲荷神社に行ってはいけない人の特徴は以下の7つです。
それぞれ詳しく解説しますので、自分に当てはまるのかどうか確認してみてください。
神様への信仰心や感謝の気持ちがない人
稲荷神社に行ってはいけない人の1つ目は「神様への信仰心や感謝の気持ちがない人」です。
なぜなら、神社は神様に対する信仰心や感謝の気持ちを大切にする場所だからです。
神社では神様に感謝を表すことがとても重要。神様は感謝の気持ちを汲み取り、その気持ちに応えてくれるとされているのです。
そのため、感謝の気持ちがない人は、神様と良好な関係が築けません。
稲荷神社での参拝をより意味のあるのもにするためには、感謝の気持ちを大切にすることが重要となります。
体調が悪い人
稲荷神社に行ってはいけない人の2つ目は「体調が悪い人」です。
例えば、お参りに行こうとした日に体調を崩してしまったり、神社に近づくと気分が悪くなってしまうなどです。
こんな時は、お稲荷様からの警告かもしれません。
体調が悪い時は無理して参拝をせずに、体調を整えてから改めて訪れましょう。
ネガティブな言動が多い人
稲荷神社に行ってはいけない人の3つ目は「ネガティブな言動が多い人」です。
ネガティブな言動が多い人は、心や体の中に負のオーラを溜めていっていると言われています。
負のオーラを溜めたまま鳥居をくぐってしまうと、良いことが起こるどころか、逆に悪いものを引き寄せてしまう可能性が高いです。
まずは、前向きな感情を持つ努力をし、心身を整えた上で改めて神社に訪れましょう。
道に迷った人
稲荷神社に行ってはいけない人の4つ目は「道に迷った人」です。
稲荷神社に行こうとしても道に迷ってたどり着けない時は、今は参拝のタイミングではないという神様からのサインかもしれません。
道に迷ったときは、参拝するのではなく日々の生活を大切に過ごすようにしましょう。
稲荷神社に対して恐怖や不安を感じる人
稲荷神社に行ってはいけない人の5つ目は「稲荷神社に対して恐怖や不安を感じる人」です。
稲荷神社に対して恐怖や不安を感じた時は、無理に参拝するのは避けましょう。
恐怖心や不安はネガティブな気持ちと捉えられて、負の気を寄せ付けてしまうと言われています。
稲荷神社は感謝の気持ちや今後の平和を願うための神社です。稲荷神社に恐怖心がある人は相性がいいとは言えません。
恐怖心や不安な気持ちがなくなった時にまた足を運んでみてくださいね。
食べ物を無駄にする人
稲荷神社に行ってはいけない人の6つ目は「食べ物を無駄にする人」です。
稲荷神社にいる神様は食の神様のため、食べ物を無駄にする人は歓迎されないでしょう。
食べ物を無駄にする人は参拝してもご利益がないかもしれません。まずは、食べ物を無駄にしないよう自分の行動を見直すことが大切です。
悪いことを考えている人
稲荷神社に行ってはいけない人の7つ目は「悪いことを考えている人」です。
神社は清らかな心で参拝することが求められます。そのため、神様は悪いことを考えている人を好みません。
まずは、自分の心を浄化し前向きな気持ちを持ちましょう。そうすることで神様からのご加護を受けやすくなりますよ。
お稲荷さんに好かれる人の特徴

ここからは、お稲荷さんに好かれる人の特徴を解説していきます。
以下の4つの特徴に当てはまるとお稲荷さんに好かれてご利益を得られるかもしれません。
では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
明るく元気な人
お稲荷さんに好かれる人の特徴1つ目は「明るく元気な人」です。
明るく元気な人は負のオーラを溜めることがないため、お稲荷さんに好かれる傾向があります。
常に前向きな気持ちを持っていて、周りの人にも気を遣えることがポイントです。
困っている人にすぐ手を差し伸べれるような行動を取れる人は神様からも好意を持たれやすいですよ。
神様や仏様を心から信じている人
お稲荷さんに好かれる人の特徴2つ目は「神様や仏様を心から信じている人」です。
参拝される方の中には「願いが叶ったら、神様を信じます」という気持ちを持たれている方も少なくありません。
このような気持ちでは神様や仏様に対して失礼にあたります。
心から神様や仏様を信じている人は日頃から感謝の気持ちを持っているものです。
日常的に「ありがとう」と使える人は、神様からのご利益を受けやすくなります。
人の意見に流されやすい人
お稲荷さんに好かれる人の特徴3つ目は「人の意見に流されやすい人」です。
人の意見に流されやすいということは、他人を尊重する心を持っているということ。自分の意見を押し通すのではなく、人の意見にも耳を傾ける姿勢がポイントですよ。
食べ物に興味があり、農業に関わっている人
お稲荷さんに好かれる人の特徴4つ目は「食べ物に興味があり、農業に関わっている人」です。
お稲荷さんは食物や農業の神様であるため、食べ物を大切にし、農業に携わる人を好みます。
食べ物のありがたさを感じている人や農作物を大切に育てている人は、お稲荷さんのご利益を受けやすいです。
稲荷神社の参拝で気を付けるべきこと

稲荷神社の参拝をする際に気を付けるべきこともあります。
これらを守らないと、悪いことが起きてしまう可能性もあるので、しっかりチェックしておいてくださいね。
稲荷神社では神様を守る狐が眷属として祀られているので、狐が嫌がることはNGとされています。
自己中心的な願い事は控える
お稲荷さんは五穀豊穣や商売繫盛など、幸せになることを願う神様です。
そのため、自己中心的な願い事は良くないとされています。
参拝する時は、家族など周りの人々が一緒に幸せになれるようなことをお願いするようにしましょう。
ペットを連れていかない
稲荷神社は基本的にペット連れの参拝は禁止されています。
特に、犬は狐と相性が悪いため連れていくとケンカになると言われています。
家族と一緒に訪れてる場合は交代して参拝するなど工夫し、境内には連れて行かないようにしましょう。
ただし、介助犬や盲導犬などは許可されているケースもあるので、事前に神社に確認してみてくださいね。
肉や魚を持ち込まない
稲荷神社を参拝する際、肉や魚を持って行くのもやめておきましょう。
生肉は動物霊を引き寄せるとされており、狐憑きの原因になる可能性が高いです。
近所に稲荷神社があれば買い物帰りに参拝したくなる人もいるかもしれませんが、肉や魚を持っているときは、一度家に置いてから出直してくださいね。
ライターやタバコを持ち込まない
稲荷神社の狐は火気を嫌がります。
特に、ライターやタバコなどの火気を持ち込むことは避けてください。参拝する前にポケットや鞄の中を確認しておきましょう。
また、神社の近くでタバコに火をつけるのもよくありませんので、参拝するときは注意してくださいね。
夕方以降の参拝は避ける
神社で決められている参拝時間内なら問題ありませんが、夕方以降は悪い影響を受けやすい時間帯とされているため避けるようにしましょう。
また、稲荷神社は山の中にあることも多く、暗くなると足元が見づらなるため転んでケガをしてしまうという理由もあります。
参拝するときは、日中の明るい時間帯に訪れてくださいね。
写真撮影は決められた場所で行う
稲荷神社で写真撮影をする時もあるでしょう。しかし参道を占拠する行為は禁止となっているため、写真撮影をする時は、他の参拝者の邪魔にならない場所や決められた場所で行ってくださいね。
また「全面的に撮影禁止」「祈禱すれば撮影できる」といった撮影ルールを設けている神社もあるので、事前に電話などで確認しておくといいでしょう。
特定の時期や時間帯に訪れるのを避ける
禁止されているわけではありませんが、神社には「不成就日」や「赤口」など神社に行かない方がいい時期があります。
不成就日は「物事が成就しない日」と言われており、縁起の悪い日です。願いが成就しない日なので、参拝しても神様まで願いが届かないかもしれません。
赤口は、午前11時から午後1時の間だけ吉ですが、その他の時間帯は「凶日」とされているので何をしても支障が起きやすい日です。
縁起の良くない日は参拝を避けるようにしてくださいね。
稲荷神社に関するよくある質問|Q&A
ここからは、稲荷神社に関するよくある質問を紹介します。
稲荷神社に参拝する際の服装は?
稲荷神社に参拝する際の服装については、特に厳しい規定はありませんが、一般的なマナーとして以下の点に気をつけると良いでしょう。
- 清潔な服装
- 季節に応じた服装
- 歩きやすい履き物
神社は神聖な場所ですので、清潔な服装を心がけることが大切です。特に派手すぎる服装や露出の多い服装は避け、落ち着いた服装を選びましょう。
また、季節に応じて快適に過ごせる服装を選びましょう。夏場は涼しい服装、冬場は暖かい服装を心がけると良いです。
神社の境内は砂利道や階段が多い場合があるので、歩きやすい履き物を選びましょう。サンダルやハイヒールは避け、スニーカーやローファーなどの歩きやすい靴が適しています。
稲荷神社での適切な参拝方法は?
稲荷神社での参拝方法は、基本的には他の神社と同様ですが、以下の手順を守ると良いでしょう。
- STEP
鳥居をくぐる
鳥居をくぐる際は一礼し、真ん中を避けて歩きましょう。鳥居の中央は神様の通り道とされているためです。
- STEP
手水舎での清め
手水舎で手と口を清めます。右手で柄杓を持ち、左手、右手の順に清め、左手に水を受けて口をすすぎます。再度左手を清め、最後に柄杓の柄を立てて柄を清めます。
- STEP
参道を進む
参道の中央を避けて歩きます。中央は神様の通り道とされるため、端を歩くようにしましょう。
- STEP
お賽銭
賽銭箱にお賽銭を入れます。額に決まりはありませんが、心を込めてお供えしましょう。
- STEP
二礼二拍手一礼
賽銭箱の前で軽くお辞儀し、二回深く礼をします。その後、二回手を叩き、再び深く礼をします。この際、自分の願い事や感謝の気持ちを心の中で伝えましょう。
稲荷神社でのお守りの扱い方は?
お守りの扱い方については、以下の点に注意すると良いでしょう。
- 常に持ち歩く
- 大切に扱う
- 一年ごとのお焚き上げ
- 返納の方法
お守りは常に身につけて持ち歩くのが基本です。したがって、バッグの中やポケットなど、自分の近くに置いておきましょう。
また、お守りは神聖なものですので、丁寧に扱うことが重要です。汚れたり破損したりしないように注意してください。
お守りの効果は一般的に一年間とされています。ですから、一年経ったら感謝の気持ちを込めて神社に返納し、新しいお守りを受けると良いでしょう。この際、「お焚き上げ」をお願いすることができます。
さらに、返納する際は、神社の専用の返納箱に入れるか、神社の職員に直接渡しましょう。郵送で返納を受け付けている神社もあるため、遠方の場合は事前に問い合わせてみると良いでしょう。
まとめ
今回は、稲荷神社に行ってはいけない人の特徴や怖いと感じる理由について紹介してきました。
- 稲荷神社は狐を使いとした神社
- 稲荷神社が怖いと言われる理由は祟りや狐の眷属が動物霊であるのが関係している
- 稲荷神社に行ってはいけない人がいる
- お稲荷さんに好かれる人には特徴がある
- 稲荷神社で参拝するときの注意点がある
稲荷神社は日本各地にあり、身近な存在です。
怖いとも言われてますが、神様を信じて参拝すればたくさんのご利益を授けてくれますよ。
ただ、参拝時には注意しなくてはならないこともあるので、この記事を参考にして参拝へ訪れてくださいね。