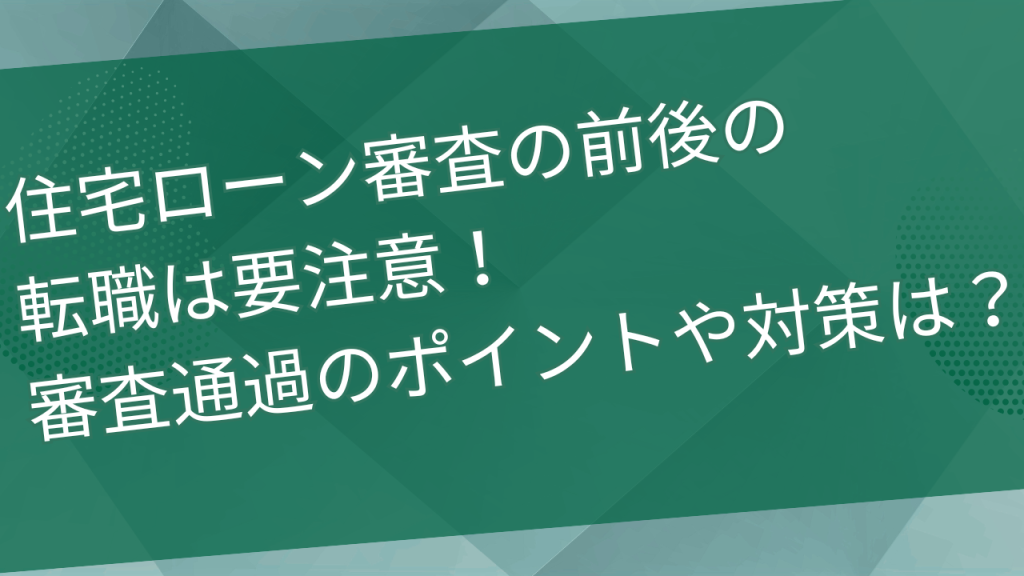
マイホーム購入を検討している方にとって、住宅ローンの審査に通るかどうかは大きな関心事ですよね。特に転職を考えている方や転職したばかりの方は「住宅ローン審査に通るだろうか?」と不安を感じているのではないでしょうか。
実は、住宅ローンの審査において転職は非常に重要なファクターとなります。転職のタイミングによっては審査に通りにくくなるケースもあれば、逆に有利に働くケースもあるんです。
この記事では、住宅ローン審査と転職の関係について詳しく解説します。転職が審査に与える影響や、審査に通りやすくなるタイミング、審査に通らない場合の対策までをまとめました。マイホーム購入と転職の両立を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
住宅ローンを簡単に比較してあなたにぴったりの金利の安い銀行が探せる!
モゲチェックだけの優遇金利でお得に借りよう!
↓↓↓↓↓
目次
転職が住宅ローン審査に与える影響
「転職したら住宅ローンの審査に通らないのでは?」
このように心配する方は多いと思います。結論からいうと、転職は基本的に住宅ローンの審査において不利に働くケースが多いです。でも、なぜ転職が審査に影響するのでしょうか?
転職が審査に不利に働く理由
住宅ローン審査の本質は「この人は長期間にわたって安定的に返済できるか?」を見極めることです。金融機関にとって、安定した返済能力の判断材料となるのが「勤続年数」なんですね。
転職すると、基本的に勤続年数はリセットされます。国土交通省の「令和4年度民間住宅ローンの実態に関する調査」によると、実に93.2%もの金融機関が審査項目として勤続年数を重視しているという結果が出ています。
つまり、転職によって勤続年数が短くなると「この人は収入が安定していない可能性がある」と判断され、審査に不利になるわけです。
金融機関が重視する返済能力の評価基準
住宅ローンの審査では、以下のような項目が重視されます
- 完済時年齢(98.5%の金融機関が重視)
- 健康状態(96.6%)
- 借入時年齢(96.0%)
- 年収(94.0%)
- 勤続年数(93.6%)
上記の数字からもわかるように、勤続年数は金融機関が非常に重視する項目の一つです。長期間同じ会社で働いているということは、その会社での雇用が安定していると判断され、その結果として収入も安定していると評価されるんですね。
逆に転職を繰り返す人は「将来的に転職する可能性が高く、収入が不安定になるリスクがある」と判断されがちです。そのため、転職直後は住宅ローンの審査において不利な立場に立たされることが多いんです。
ただし、これはあくまで一般論。転職の内容や状況によっては、必ずしも不利になるとは限りません。この点については後ほど詳しく説明します。
住宅ローン審査で最重要視される勤続年数
前章でも少し触れましたが、住宅ローンの審査において勤続年数はかなり重要な審査項目です。では、実際にどのくらいの勤続年数があれば安心なのでしょうか?
金融機関が求める一般的な勤続年数
多くの金融機関では、最低でも1年以上の勤続年数を求めています。ただし、これはあくまで最低ライン。審査を有利に進めたいなら、3年以上の勤続年数があると安心です。
特に大手銀行や信用金庫などの金融機関では、勤続年数の基準が厳しいことが多いです。一方で、ネット銀行やノンバンクなどは、比較的勤続年数の条件が緩いケースもあります。
勤続年数が住宅ローン審査に及ぼす具体的な影響
勤続年数が住宅ローン審査に与える影響は以下のようなものがあります
- 借入可能額への影響:勤続年数が短いと、借入可能額が制限される場合があります。
- 金利への影響:勤続年数が短いと、リスクヘッジとして金利が高めに設定されることもあります。
- 審査の厳しさ:勤続年数が短いと、他の条件(年収や自己資金など)がより厳しく見られることがあります。
たとえば、同じ年収500万円の人でも、勤続10年の人と勤続6か月の人では、前者の方が審査で有利になることが一般的です。これは、長期的な収入安定性の面で信頼度が異なるためです。
勤続年数の計算方法
勤続年数の計算方法は金融機関によって異なりますが、一般的には「現在の会社での就業期間」となります。ただし、以下のようなケースでは特殊な計算がされることもあります:
- グループ会社内の転籍:同一グループ内での異動は、勤続年数がリセットされない場合があります。
- 関連会社への出向:出向の場合も、元の会社からの在籍期間が継続しているとみなされることが多いです。
- 業務委託から正社員への転換:同じ会社で業務委託から正社員になった場合、業務委託期間も勤続年数に含めることがある場合もあります。
自分の勤続年数がどのように計算されるのか不安な場合は、事前に金融機関に確認しておくことをおすすめします。
「こういう状況だけど、勤続年数はどう計算されますか?」と素直に聞いてみましょう。親身に相談に乗ってくれるはずです。
転職後に住宅ローン審査に通りにくいケース
転職したからといって、必ずしも住宅ローン審査に落ちるわけではありません。しかし、以下のようなケースでは特に審査に通りにくくなる傾向があります。
短期間で複数回転職している場合
「転職を繰り返している人」は住宅ローンの審査において非常に不利になります。特に3年以内に複数回の転職歴がある場合、金融機関からは「職場定着性が低い」と判断され、将来的な収入の安定性に疑問符がつけられてしまいます。
一例ですが、3年間で3社を渡り歩いた後に住宅ローンを申請したところ、大手銀行で審査落ちを経験したという例もあります。
結局、審査基準がやや緩いネット銀行で何とか審査に通りましたが、希望額より500万円ほど少ない融資額に抑えられていました。
全く異なる業種への転職
IT企業から飲食店に転職したなど、全く異なる業種への転職も審査において不利に働きます。これは「専門性やキャリアの一貫性がない」と判断され、将来的な収入安定性に疑問を持たれるためです。
特に、収入が大幅に減少するような業種変更(例:営業職からアルバイトへ)は、返済能力に直結する問題として厳しく見られます。
審査中や融資実行前の転職
これは最も避けるべきケースです。住宅ローンの審査中や、審査通過後から融資実行までの間に転職すると、以下のような問題が発生します:
- 審査結果が無効となり、再審査が必要になる
- 最悪の場合、融資自体が取り消される
- 再審査の際に条件が厳しくなる可能性がある
住宅ローンの審査完了日と融資実行日の間にはタイムラグがあります。このタイムラグの間に転職すると、審査時の条件と現状が異なるため、融資が取り消されるリスクがあります。
本審査に通ったからといって安心するのはまだ早いです。
融資が実際に実行されるまでは転職を控えるべきです。「契約したから大丈夫」と思って転職してしまうと、思わぬ落とし穴にはまることになります。
転職によって年収が大幅に減少した場合
転職して年収が大幅に減少すると、返済能力が下がったと判断され、審査に通りにくくなります。
一般的に、年収に対して借入額が大きすぎると審査に通りません。
多くの金融機関では、年収の7倍程度が借入限度額の目安となります(金融機関によって異なります)。例えば、転職前は年収800万円だったのに、転職後は年収500万円になった場合、借入可能額が大幅に減少する可能性があります。
年収が下がったのに高額な住宅ローンを組もうとすると、毎月の返済額が家計を圧迫し、返済が滞るリスクが高まります。金融機関はそのリスクを回避するために、年収に見合った借入額に制限するわけです。
転職後でも住宅ローン審査に通りやすいケース
ここまで転職が審査に不利に働くケースを説明してきましたが、すべての転職が悪影響を及ぼすわけではありません。むしろ、審査に有利に働く転職もあるんです。
グループ会社内での異動や出向
同じグループ会社内での異動や出向の場合、多くの金融機関では「転職」とはみなさず、勤続年数がリセットされません。
このケースでは、形式上は会社が変わっても、勤続年数が継続しているとみなされるため、住宅ローン審査に悪影響を及ぼすことはほとんどありません。むしろ、転籍によって年収が上がるなら、審査においてプラスに働くこともあります。
ただし、必ず金融機関に「グループ会社内での異動である」ことを事前に伝え、必要な証明書類(辞令コピーなど)を準備しておくとスムーズです。
同業界でのキャリアアップ転職
前職と同じ業界での転職、特に年収アップを伴うキャリアアップの場合は、審査において比較的有利に働く可能性があります。
例えば、中小のIT企業から大手ITベンダーへの転職で年収が100万円アップしたといったケースです。このような転職は、キャリアパスに一貫性があり、計画的な転職と判断されやすいため、金融機関からの評価も悪くならないことが多いです。
転職による年収アップは、返済能力の向上につながるため、プラス要素として評価されることもあります。ただし、それでも勤続年数は短くなるため、転職直後よりも、ある程度の期間(半年〜1年程度)働いてから申し込む方が無難です。
ヘッドハンティングによる転職
ヘッドハンティングによる転職も、住宅ローン審査において比較的有利に働く可能性があります。なぜなら、ヘッドハンティングは「市場価値の高い人材」に対して行われるものであり、専門性やスキルが高く評価されている証拠だからです。
特に年収アップを伴うヘッドハンティング転職の場合、金融機関からも「安定した雇用が期待できる」と判断されやすくなります。
ただし、ヘッドハンティングであっても転職回数が多いと、職場定着性の問題で不利に働く可能性があるので注意が必要です。理想的には、ヘッドハンティングで転職した後、半年から1年程度はその会社で勤務してから住宅ローンを申し込むと良いでしょう。
勤続年数の要件がない住宅ローン商品の利用
転職後でも審査に通りやすい住宅ローン商品も存在します。代表的なものとしては、フラット35が挙げられます。
フラット35は、住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利型の住宅ローンですが、勤続年数を申し込み要件としていません。そのため、転職後すぐでも申し込むことができ、比較的審査に通りやすい傾向があります。
また、一部のネット銀行やノンバンクでも、勤続年数の条件が緩い住宅ローン商品があります。ただし、金利が若干高めに設定されていることもあるので、トータルコストを考慮して検討する必要がありますね。
住宅ローン申込みのベストなタイミング
転職を考えている方は、住宅ローンをいつ申し込むべきか悩むところだと思います。ここでは、住宅ローン申込みのベストなタイミングについて解説します。
転職前か転職後か、どちらが有利?
結論からいうと、次のようになります。
- 転職によって年収が上がるなら:転職後、新しい職場で安定してから申し込む
- 転職によって年収が下がるなら:転職前に申し込む
- 転職は未定だが近い将来可能性があるなら:融資実行まで待ってから転職する
例えば、年収600万円から800万円に上がる転職なら、転職後に申し込む方が借入可能額が増える可能性があります。ただし、その場合でも最低半年〜1年は新しい職場で働いてから申し込むのが無難です。
逆に年収が下がる転職の場合、転職前に申し込んだ方が借入可能額が大きくなります。ただし、審査中や融資実行前に転職するのはNGなので、融資実行までは転職しないよう注意しましょう。
転職後、何ヶ月待てば審査に有利?
転職後に住宅ローンを申し込む場合、一般的には以下のタイミングが目安となります:
- 最低ライン:転職後6ヶ月経過
- 理想的なタイミング:転職後1年以上経過
- より有利なタイミング:転職後2〜3年経過
多くの金融機関では、勤続年数1年以上を一つの基準としています。転職後、最低でも半年、できれば1年以上は同じ会社で働いてから住宅ローンを申し込むのが理想的です。
この期間、あなたは「新しい職場で安定した働きぶりを示す時間」を作っていることになります。また、この待機期間中に頭金を増やしたり、他のローンを減らしたりすることで、審査の通過率を上げることもできます。
事前に金融機関に相談するメリット
転職を控えている場合や転職後間もない場合、いきなり住宅ローンを申し込むのではなく、まずは金融機関に相談することをおすすめします。
多くの金融機関では無料相談を実施しており、あなたの状況に合わせたアドバイスを受けることができます。例えば:
- 「転職後何ヶ月経てば申し込めますか?」
- 「この転職は審査にどう影響しますか?」
- 「転職前と後、どちらで申し込む方が有利ですか?」
などの質問に、具体的に回答してもらえるはずです。
事前相談のメリットは、正式な審査申込前に自分の状況を把握できることです。もし転職が審査にネガティブな影響を与えそうなら、申込のタイミングを調整したり、別の金融機関を検討したりする余地が生まれます。
「事前相談→仮審査→本審査→融資実行」というステップを踏むことで、審査落ちのリスクを最小限に抑えることができます。特に転職を控えている方や転職直後の方は、必ず事前相談を活用してください。
住宅ローン返済中に転職する際の注意点
すでに住宅ローンを借りている場合でも、転職は慎重に行う必要があります。住宅ローン返済中に転職する際の注意点を解説します。
金融機関への申告義務
多くの人が知らないのですが、住宅ローン返済中に転職した場合、金融機関への申告義務があります。これは住宅ローン契約書の約款に記載されていることが一般的です。
「別に言わなくても毎月きちんと返済してるし大丈夫でしょ」と思うかもしれませんが、実はそうではありません。住宅ローンの契約書には、勤務先や収入に変更があった場合は速やかに報告するよう定めている条項があるんです。
申告を怠ると、最悪の場合「期限の利益の喪失」(一括返済を求められる)というペナルティを受ける可能性もあります。転職したら、必ず金融機関に連絡し、指示に従って必要書類を提出しましょう。
収入減となった場合の対応策
転職によって収入が減少し、住宅ローンの返済が厳しくなった場合、以下のような対応策が考えられます:
- 返済期間の延長:月々の返済額を減らすために、返済期間を延長する方法です。ただし、総返済額は増えます。
- ボーナス返済の見直し:ボーナス払いを減額または中止し、毎月の返済に振り分ける方法です。
- 繰上返済(返済額軽減型):まとまった資金があれば、元金を一部返済して月々の返済額を減らす方法です。
- 借り換え:金利の低い別の金融機関に借り換えて、返済負担を軽減する方法です。
いずれにしても、返済が厳しくなる前に金融機関に相談することが重要です。返済が滞ってからでは対応が難しくなるので、収入減が確定した時点で早めに相談しましょう。
住宅ローン控除の手続き変更
住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受けている方が年の途中で転職した場合、手続き方法が変わる場合があります。
- 同一年内に転職し、年末までその会社で働いている場合:転職先の会社で年末調整の際に住宅ローン控除の手続きができます。このとき、前職の源泉徴収票が必要になります。
- 退職後に再就職せず年末を迎えた場合:確定申告で住宅ローン控除の手続きを自分で行う必要があります。
住宅ローン控除は最大で年間40万円(借入残高の1%)の税金が戻ってくる大きなメリットです。転職によって手続きを忘れると、このメリットを受けられなくなるので注意しましょう。
特に確定申告が必要なケースでは、自分で税務署に行くか電子申告(e-Tax)で手続きする必要があります。期限(通常は翌年の2月16日から3月15日まで)を過ぎると申告できなくなるので、スケジュール管理も重要です。
転職後に住宅ローンを申し込む際の注意点
転職後に住宅ローンを申し込む場合、いくつかの注意点があります。審査を有利に進めるためのポイントを解説します。
審査に通りにくくなるリスク
転職後すぐに住宅ローンの審査を受けると、一般的には審査に通りにくくなります。特に注意すべきは以下の点です:
- 審査に落ちると、他の金融機関の審査にも影響する可能性がある
- 金融機関が共有する信用情報に「住宅ローン審査落ち」の記録が残る
- 短期間に複数の審査を受けると、さらに不利になる
したがって、転職後すぐに複数の金融機関に申し込むのではなく、ある程度の期間を置いてから、慎重に金融機関を選んで申し込むことをおすすめします。可能であれば、事前相談で通過可能性を確認してから正式に申し込むとよいでしょう。
希望額を借りられない可能性
転職後でも審査に通る場合がありますが、希望する金額を借りられない可能性があります。勤続年数が短いことでリスクが高いと判断され、借入希望額よりも低い金額しか融資してもらえないケースもあるんです。
例えば、5,000万円の借入を希望していても、審査の結果「4,000万円までなら貸せます」と言われることもあります。そうなると、頭金を追加で用意するか、予算を下げて物件を探し直すかの選択を迫られることになります。
特に転職によって年収が下がった場合、借入可能額も下がる可能性が高いので注意が必要です。
必要書類の増加
転職後に住宅ローンを申し込むと、通常より多くの書類提出を求められることがあります。具体的には以下のような書類です
- 採用通知書・雇用契約書:転職先の会社での雇用条件が確認できる書類
- 勤務先発行の勤続証明書:実際に働いている期間を証明する書類
- 見込収入証明書:今後の収入見込みを示す書類(転職後1年未満の場合に必要)
- 転職後の給与明細書:実際に給与が支払われていることを証明する書類(数ヶ月分)
- 職歴書:これまでの職歴を示す書類(転職を繰り返している場合に特に重要)
これらの書類を用意するのは意外と手間がかかります。特に見込収入証明書は会社によっては発行に時間がかかったり、発行自体を断られたりすることもあるので、早めに準備を始めることをおすすめします。
また、審査中に追加書類を求められることも珍しくありません。「なんで転職したのか」「なぜこの会社を選んだのか」などの質問に答える説明書の提出を求められることもあるんですよ。
転職後の収入安定性をアピールする方法
転職後でも審査を有利に進めるためには、収入の安定性をアピールすることが大切です。以下のようなポイントを意識してみましょう:
- 同業種・同職種へのキャリアアップであることを強調:職務経歴書などで、一貫したキャリアパスであることをアピールする
- 正社員としての雇用形態であること:契約社員や派遣社員より、正社員の方が審査では有利
- 大手企業や上場企業への転職:会社の安定性も評価対象になるため、知名度の高い企業への転職はアピールポイント
- 年収アップを証明する:転職前より収入が増えていれば、返済能力の向上として評価される
これらのポイントを書類や面談で積極的にアピールすることで、転職後でも審査を通りやすくなる可能性があります。自己アピールのためのPR文書を別途用意しておくのも効果的ですね。
転職と住宅ローンを両立させるための具体的な戦略
ここまで転職と住宅ローンの関係について詳しく見てきましたが、最後に「どうすれば転職と住宅ローンを上手に両立できるか」について、具体的な戦略をお伝えします。
転職前に住宅ローンを組む場合のシナリオ
転職前に住宅ローンを組むシナリオを選ぶ場合、以下のステップを踏むとよいでしょう:
- 転職準備と並行して住宅ローンの申込準備を進める:物件探し、必要書類の収集などを始める
- 住宅ローンの仮審査を受ける:転職前の収入と勤続年数で審査を受ける
- 本審査・契約締結まで進める:転職前に本審査・契約まで完了させる
- 融資実行を確認:実際に融資金が振り込まれたことを確認する
- その後転職活動を本格化:融資実行後に転職活動を本格化させる
注意点は、融資実行前に内定を受けていても、その事実を金融機関に伝えないことです。内定を得ていることが分かると、融資実行が保留になる可能性があります。もちろん嘘をつくわけではなく、単に「現時点では転職の予定はありません」と答えるのが無難です。
ただし、融資実行直後の転職は、前述したような契約違反のリスクもあります。融資実行から最低でも数ヶ月は経過してから転職するのがベストです。
転職後に住宅ローンを組む場合のシナリオ
転職後に住宅ローンを組むシナリオを選ぶ場合、以下のステップを踏むとよいでしょう:
- 転職後、最低6ヶ月は新しい職場で働く:勤続期間を確保する
- その間に頭金を増やす:貯蓄を増やし、借入額を減らす
- 勤続年数の条件が緩い金融機関を探す:フラット35やネット銀行などを中心に
- 事前相談を活用する:正式申込前に複数の金融機関で相談する
- 必要書類をしっかり準備:転職後に必要な追加書類も用意する
- 仮審査→本審査の流れで申し込む:一発で本審査に申し込まず、まず仮審査で可能性を探る
転職後のシナリオでは、特に「複数の金融機関に同時に申し込まない」ことが重要です。一つの金融機関で仮審査を受け、通過できそうなら本審査に進む。通過が難しそうなら別の金融機関に相談する、という流れがベストです。
理由は、短期間に複数の審査申込をすると、信用情報機関に「複数の借入申込あり」と記録され、さらに審査が不利になる可能性があるからです。
住宅購入を先にすべきか、転職を先にすべきか
結局のところ、住宅購入を先にすべきか、転職を先にすべきかは、以下のポイントで判断するとよいでしょう:
住宅購入を先にすべきケース:
- 現在の勤続年数が長く、審査で有利な立場にある場合
- 転職で年収が下がる可能性がある場合
- 既に物件が決まっていて、早急に購入する必要がある場合
- 住宅ローンの金利が上昇傾向にあり、早めに固定したい場合
転職を先にすべきケース:
- 転職によって年収が大幅に上がる見込みがある場合
- 現在の勤続年数が短く、どちらにしても審査が厳しい場合
- 転職先の方が雇用が安定している場合(例:中小企業から大企業へ)
- 物件探しをこれから始める段階で、時間的余裕がある場合
正直なところ、転職と住宅購入の両方を短期間で行うのはかなりリスクが高いです。どうしても両方を近いタイミングで行いたい場合は、プロの意見を聞くことをおすすめします。ファイナンシャルプランナーや住宅ローンアドバイザーに相談し、自分の状況に合った最適な順序とタイミングを決めましょう。
よくある質問(FAQ)
最後に、転職と住宅ローンに関してよくある質問に答えます。
Q
転職予定があることを金融機関に伝えるべきですか?
A
原則として、住宅ローンの審査中や融資実行前に転職予定があるなら、金融機関に伝えるべきです。万が一、黙っていて後から発覚すると、融資取り消しや契約違反とみなされる可能性があります。
ただし、現時点で具体的な転職先が決まっておらず、単に「いつか転職したい」という程度であれば、伝える必要はありません。
Q
派遣社員から正社員への転職は住宅ローン審査に有利ですか?
A
はい、有利に働く可能性が高いです。雇用形態が不安定な派遣社員から、安定した正社員への転換は、収入の安定性向上として評価されやすいです。ただし、やはり正社員になってからある程度の期間(半年〜1年)は勤務してから申し込むのが望ましいです。
Q
フリーランスへの転身を考えていますが、住宅ローンは組めますか?
A
フリーランスでも住宅ローンを組むことは可能ですが、会社員と比べると条件は厳しくなります。一般的には、フリーランスとして最低2〜3年の実績(確定申告書)が必要で、安定した収入があることを証明する必要があります。
もしフリーランスへの転身を検討しているなら、会社員のうちに住宅ローンを組んでおくか、フリーランスとして実績を積んでから申し込むか、どちらかの選択肢が現実的です。
Q
住宅ローン審査の「勤続年数」は、同じ会社での勤務期間ですか?それとも同じ業種での勤務期間ですか?
A
基本的には「同じ会社での勤務期間」を指します。ただし、金融機関や審査基準によっては、同じ業種での経験年数も考慮されることがあります。特に、専門職(医師、弁護士など)の場合は、転職しても同じ職業であれば、職歴全体が考慮されるケースもあります。
Q
仮審査は通ったのに本審査で落ちることはありますか?
A
はい、あります。仮審査は簡易的な審査で、主に申告内容をもとに判断されます。一方、本審査では詳細な書類確認や信用情報の照会が行われるため、仮審査では見えなかった問題(例:過去の延滞履歴、他のローンの存在など)が発見されて審査落ちすることがあります。
特に転職直後の場合、仮審査では「勤務先アリ」として通ったとしても、本審査で勤続年数が短いことが判明し、審査落ちになるケースもあります。
Q
住宅ローンの審査中に内定が決まった場合、どうするべきですか?
A
基本的には、融資実行まで内定の事実を金融機関に伝えないことをおすすめします。融資実行前に伝えると、審査のやり直しや融資の保留などのリスクがあります。
ただし、融資実行後は速やかに転職の事実を伝える必要があります。特に契約書に「勤務先変更時の報告義務」が明記されている場合は、報告を怠ると契約違反になる可能性があります。
Q
住宅ローン控除は転職すると受けられなくなりますか?
A
いいえ、転職しても住宅ローン控除は継続して受けられます。ただし、手続き方法が変わることがあります。
年の途中で転職し、年末まで新しい会社で働いている場合は、転職先の年末調整で手続きができます(前職の源泉徴収票が必要)。一方、退職後に再就職していない場合は、確定申告で手続きをする必要があります。いずれにしても、手続きを忘れないようにしましょう。
まとめ:転職と住宅ローンは「タイミング」がすべて
この記事では、住宅ローン審査に転職が与える影響と、その対策について詳しく解説してきました。
結局のところ、転職と住宅ローンを両立させる最大のポイントは「タイミング」です。転職直後の住宅ローン申込みは避け、転職から最低でも半年、できれば1年以上経ってから申し込むのが理想的です。
また、住宅ローンの審査中や融資実行前の転職は絶対に避けるべきです。万が一のときのリスクが非常に大きいからです。
一方で、すべての転職が住宅ローンにネガティブな影響を与えるわけではありません。同業種でのキャリアアップや年収アップを伴う転職なら、むしろポジティブに評価される可能性もあります。
大切なのは、金融機関に隠し事をせず、自分の状況を正直に伝えて相談することです。多くの金融機関では、様々なケースに対応した住宅ローン商品を用意しています。あなたの状況に合った最適なプランを提案してもらえるはずです。
転職と住宅購入は、どちらも人生の大きな決断です。焦らず、計画的に、そして信頼できる専門家のアドバイスを参考にしながら進めていきましょう。
