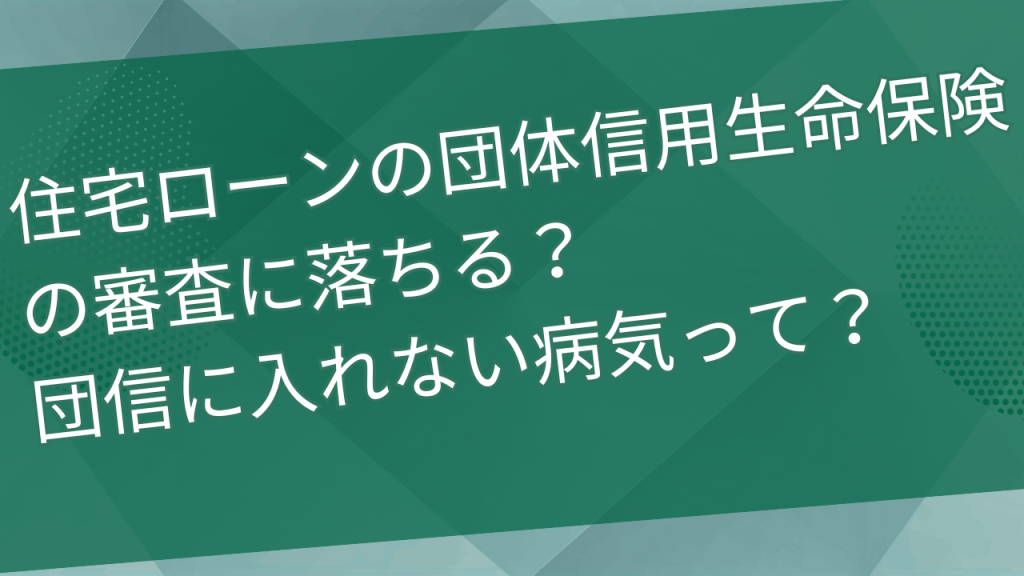
住宅ローンを組むとき、審査に通るか不安になりますよね。特に持病や病歴がある方は「団体信用生命保険(団信)の審査に通らないかも…」と心配されるかもしれません。
実は住宅ローン審査において、健康状態は極めて重要な要素なんです。国土交通省の調査によると、融資審査で考慮される項目のうち「健康状態」は第2位に位置づけられているほど。
でも、病気があるからといって必ずしも団信に入れないわけではありません。この記事では、団信審査に影響する病気の種類や、万が一審査に落ちた場合の対処法まで、徹底的に解説していきます。
住宅購入を控えている方や、健康面に不安がある方は、ぜひ参考にしてくださいね。
住宅ローンを簡単に比較してあなたにぴったりの金利の安い銀行が探せる!
モゲチェックだけの優遇金利でお得に借りよう!
↓↓↓↓↓
目次
団体信用生命保険(団信)とは?仕組みを理解しよう
住宅ローンの話を聞くと必ず出てくる「団信」という言葉。正式名称は「団体信用生命保険」といいます。これがないと住宅ローンが組めないというケースが多いんですが、いったい何なのでしょうか?
団信の基本的な仕組み
団信とは、住宅ローンの契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、残りの住宅ローン残高を保険金で返済してくれる保険制度です。
わかりやすく言うと、「もしものときに、家族が住宅ローンの返済に困らないようにする保険」というわけです。
団信の契約では:
- 保険契約者・受取人:金融機関
- 被保険者:住宅ローン契約者
- 保険料:一般的に金利に含まれていることが多い
このような形で契約が結ばれます。住宅ローン契約者が亡くなったり高度障害状態になったりした場合、保険会社が残りのローン債務を金融機関に支払い、完済扱いになるんですね。
なぜ団信が住宅ローンに必要なのか
「なんで団信に入らないといけないの?」と思う方もいるかもしれませんね。
実は、団信は金融機関にとっても、借り手にとってもメリットがあるんです。
金融機関側は、借り手に万が一のことがあっても確実にローンが返済されるため、貸し倒れリスクを減らせます。一方、借り手側は、自分に何かあっても家族がローン返済に苦しむ心配がなくなります。
そのため、ほとんどの民間金融機関では、住宅ローン契約時に団信への加入を必須条件としています。融資を受けるためには、団信の審査にも通過する必要があるわけですね。
団信の種類と特徴
団信には主に3種類あります。自分の健康状態や保障内容に応じて、適切なものを選ぶことが大切です。
| 種類 | 特徴 | 保障内容 |
|---|---|---|
| 一般団信 | 基本的な団信 | 死亡・高度障害のみ |
| ワイド団信 | 引受条件が緩和された団信 (健康上の理由で一般団信に入れない人向け) | 死亡・高度障害のみ (金利は一般団信より0.2〜0.3%高い) |
| 疾病保障付き団信 | 一般団信に特定疾病の保障を追加 | 死亡・高度障害に加え、がんや3大疾病など |
「健康に自信がない…」という方は、ワイド団信を検討するのもひとつの選択肢です。ただし、金利が上乗せされる点はデメリットとして覚えておきましょう。
団信審査に落ちる可能性がある病気・健康状態とは
「どんな病気があると団信の審査に落ちるの?」これは多くの方が気になるポイントですよね。ここでは、団信審査に影響する可能性のある主な病気や健康状態について解説します。
告知が必要な主な病気
団信の申込時には健康状態の告知が必要ですが、特に以下のような病気は要注意です。
| 身体の部位/系統 | 告知が必要な主な病気 |
|---|---|
| 心臓・血圧 | 高血圧症、不整脈、狭心症、心筋梗塞、心不全など |
| 脳・精神・神経 | 脳卒中、精神病、うつ病、神経症、てんかん、自律神経失調症、アルコール依存症など |
| 胃腸 | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病など |
| 肝臓・膵臓 | 肝機能障害、肝炎、肝硬変、すい炎など |
| 腎臓 | 腎炎、ネフローゼ、腎不全、のう胞腎など |
| 内分泌・代謝異常 | 糖尿病、甲状腺の病気、脂質異常症など |
| 目 | 緑内障、網膜の病気、角膜の病気など |
| がん | ポリープ、上皮内新生物、がん、肉腫、白血病、しゅよう、悪性リンパ腫など |
| その他 | リウマチ、こうげん病、貧血症、子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫など |
「えっ、これだけあるの!?」と驚かれるかもしれませんね。ただ、ここに挙げた病気があるからといって、必ずしも審査に落ちるわけではありません。大切なのは、その病気の状態や程度です。
審査に通りにくい健康状態
特に以下のような健康状態の場合は、審査に通りにくい傾向があります。
- 現在入院中、または入院・手術を控えている
- 告知書に記載されている傷病で現在治療中
- 検査で異常を指摘されたが、再検査や精密検査を受けていない
- がんや重篤な疾患で治療中
- 生命に関わる持病がある
ただし、「絶対に通らない」というわけではありません。例えば、病状が軽度である場合や、治療が終わって時間が経過している場合は、審査に通る可能性も十分あります。
私の知人も、5年前に手術した甲状腺の病気があったのですが、きちんと告知した上で審査に通過した例もあります。過去の病歴があっても、現在の状態が安定していれば大丈夫なケースは多いんです。
団信の告知書に正直に書くべき?記入時の注意点
「持病があると団信に入れないかも…だから黙っておこうかな」
こんな考えが頭をよぎる方もいるかもしれませんが、これは絶対にやってはいけません。ここでは、告知書の書き方と注意点について詳しく解説します。
告知書で求められる情報
団信の告知書では、一般的に以下の情報を記入することが求められます。
- 告知書記入日から過去3ヵ月以内の治療・投薬歴
- 告知書記入日から過去3年以内の手術・治療歴
- 現在の健康状態・身体障がいの情報
「3ヵ月や3年も前のこと、覚えてないよ…」という方も多いでしょう。そんなときは、診断書やお薬手帳を確認したり、かかりつけ医に相談したりして、正確な情報を記入するようにしましょう。
告知書記入時の3つの注意点
①既往歴は詳しく記入する
病名だけでなく、以下のような情報も可能な限り詳しく記入しましょう。
- 受けた検査の種類
- 検査結果の数値
- 通院状況(頻度や期間)
- 投薬履歴と投薬量
- 現在の状態
「この情報を書いたら不利になるかも…」と思うかもしれませんが、逆に詳しく書くことで「管理されている病気」と判断され、審査に有利に働くこともあるんです。
②虚偽の情報は絶対に書かない
これが最も重要なポイントです。虚偽の情報を記入すると、「告知義務違反」となり、後々大きな問題になります。
例えば、告知義務違反が発覚した場合:
- 契約が解除される
- 保険金が支払われない
- 住宅ローンの一括返済を求められる可能性がある
- 最悪の場合、家を失うリスクもある
「たかが告知書じゃん」と軽く考えずに、正直に記入することが大切です。
③問われている質問にだけ答える
告知書に書かれている質問以外のことまで書く必要はありません。例えば:
- 告知期間外(3年以上前)の病歴
- 完治している軽微な病気(かぜやインフルエンザなど)
- 保険会社が告知対象としていない病気
これらについては記入不要です。必要以上の情報を書いて、かえって審査に不利にならないように注意しましょう。
うっかりミスを防ぐための対策
「意図的ではないけど、うっかり書き忘れたらどうしよう…」と心配な方もいますよね。そんなうっかりミスを防ぐためのポイントをご紹介します。
- 記憶で書かない:お薬手帳や診断書を確認しましょう
- 疑問点は保険会社に確認:Webで検索するより確実です
- 複雑な病歴がある場合:健康診断結果証明書を医師に書いてもらうのもひとつの方法です
ちょっとした確認不足が大きなトラブルにつながることもあります。不安な点は必ず保険会社に問い合わせましょう。
持病別の団信審査への影響と実例
ここからは、代表的な病気について、団信審査にどう影響するのかを具体的に見ていきましょう。「自分の病気は大丈夫かな?」と不安な方の参考になれば幸いです。
高血圧症の場合
高血圧は日本人に多い生活習慣病で、患者数は1,500万人以上といわれています。では、高血圧の人は団信に入れないのでしょうか?
結論からいうと、高血圧の程度によって審査結果は変わってきます。
日本高血圧学会の分類では、血圧が140/90mmHg以上で高血圧とされ、さらに以下のように細分化されています:
- I度高血圧(140〜159/90〜99mmHg)
- II度高血圧(160〜179/100〜109mmHg)
- III度高血圧(180mmHg以上/110mmHg以上)
比較的軽度なI度高血圧や、薬でコントロールされている場合は、団信に加入できる可能性が高いです。実際、私の父も高血圧で薬を服用していましたが、きちんとコントロールされていることを示す診断書を提出して、無事に審査に通ったということがありました。
ただし、II度・III度の重度の高血圧や、他の合併症がある場合は注意が必要です。
うつ病や適応障害などの精神疾患の場合
精神疾患についてはどうでしょうか?うつ病や適応障害の患者数は年々増加しており、令和2年の調査では600万人を超えています。
「精神疾患があると絶対に審査に通らない」と思われがちですが、実はそうとも限りません。
カーディフ生命の例では、うつ病の方でも一般団信の審査に通った事例があります。症状の程度や治療状況によって判断されるケースが多いようです。
特に以下のような場合は審査に通る可能性があります:
- 軽度のうつ症状である
- 薬でコントロールされており、症状が安定している
- 就労に支障がない状態である
ただし、重度のうつ病や、複数の精神疾患を抱えている場合は審査が厳しくなることもあります。
難病(潰瘍性大腸炎など)の場合
潰瘍性大腸炎などの難病を抱えている方も、住宅ローンの団信について不安を感じる方が多いのではないでしょうか。
潰瘍性大腸炎は原因が解明されておらず、完治する治療法も確立されていないため、一般団信の審査には通りにくい傾向があります。
しかし、以下のような場合は審査に通る可能性もあります:
- 現在が寛解状態である
- 症状が軽く、日常生活に支障がない
- 経過が良好であることを示す医師の診断書がある
通常の団信審査に通らなかった場合でも、ワイド団信であれば審査に通る可能性が高まります。実際に、カーディフ生命ではクローン病などの慢性的な腸の病気でもワイド団信に加入できた実績があるようです。
糖尿病の場合
糖尿病も生活習慣病の代表格ですが、どうでしょうか?
糖尿病の場合も、その程度や合併症の有無によって判断が分かれます。
- HbA1c値(糖尿病の検査値)が7.0%未満でコントロールされている
- 合併症がない
- インスリン注射を使用していない
上記のような場合は、一般団信に加入できる可能性があります。逆に、合併症がある場合や血糖値が不安定な場合は、審査に通りにくくなるかもしれません。
ただ、一般団信に通らなくても、ワイド団信であれば加入できるケースも多いです。糖尿病は、ワイド団信で引受実績のある病気の一つとして挙げられていますからね。
団信審査に落ちた場合の6つの対処法
「団信の審査に落ちてしまった…」
そんなとき、住宅ローンを諦めなければならないのでしょうか?いいえ、そんなことはありません!ここでは、団信審査に落ちた場合の対処法を6つご紹介します。
ワイド団信を利用する
もっとも一般的な対処法が、ワイド団信の利用です。
ワイド団信は、健康上の理由で一般団信に加入できない方のために設けられた、引受条件が緩和された団体信用生命保険です。
以下のような病気でも、ワイド団信なら審査に通った実績があります:
- IgA腎症やネフローゼなどの慢性的な腎臓の病気
- 慢性B型肝炎、慢性C型肝炎
- クローン病
- 心筋梗塞・狭心症(手術後経過良好な場合)
- 脳梗塞・脳出血(回復後経過良好な場合)
- 糖尿病
- うつ病
ただし、ワイド団信は通常0.2〜0.3%の金利上乗せがあるため、総返済額は増えてしまいます。例えば、3,000万円の住宅ローンを35年で組んだ場合、総返済額は数百万円増加する可能性があるため、返済計画はしっかり立てましょう。
配偶者名義で住宅ローンを組む
もう一つの選択肢は、配偶者名義で住宅ローンを組む方法です。
住宅ローンの契約者は必ずしも本人である必要はなく、配偶者が主たる債務者となることも可能です。配偶者の健康状態と収入に問題がなければ、この方法で住宅ローンを組むことができます。
この場合、団信の加入・告知も配偶者が行うため、自分の健康状態は審査に影響しません。
ただし、共働きの場合は注意が必要です。自分が病気で働けなくなった場合、収入が減少してローン返済が厳しくなる可能性も。そのため、別途就業不能保険などに加入して備えておくといいでしょう。
フラット35を利用する
住宅金融支援機構が提供するフラット35は、団信への加入が任意です。つまり、健康上の理由で団信に加入できなくても、住宅ローンを組むことが可能なんです。
フラット35のメリットは:
- 団信加入が任意である
- 全期間固定金利で将来の返済額が確定している
- 健康状態による審査への影響が少ない
ただし、団信に加入しない場合、万が一のときにローン残高の保障を受けられないため、家族の生活が困窮するリスクがあります。別途生命保険に加入するなど、リスク対策は考えておく必要があるでしょう。
他の保険会社を検討する
団信の審査基準は保険会社によって異なります。一つの保険会社で審査に落ちたとしても、他の保険会社では通る可能性があります。
金融機関によって提携している保険会社は異なるため、別の金融機関に申し込むことで、違う保険会社の団信審査を受けることができます。
ただし、審査基準は保険会社間で大きな違いはないことが多いため、同じ健康状態で審査に通る保証はありません。それでも、試してみる価値はあるでしょう。
治る病気であれば完治を待つ
一時的な病気や、完治が見込める病気の場合は、治療が終わってから住宅ローンを申し込むという選択肢もあります。
多くの団信の告知書では過去3年以内の病歴が問われるため、完治後3年経過すれば告知不要となるケースもあります。
もちろん、住宅購入の予定やタイミングによっては難しい場合もあるでしょうが、余裕がある場合は検討する価値があります。
頭金を多くする
住宅購入資金に余裕がある場合、頭金を増やして借入額を減らすという方法もあります。
借入額が少なければ金融機関側のリスクも減るため、審査に通りやすくなる可能性があります。また、借入額が少なくなれば、万が一の際の家族の負担も軽減されますよね。
どうしても団信に加入できない場合は、できるだけ多くの頭金を用意して、借入額を抑える工夫をしてみましょう。
告知義務違反のリスクと時効について
「団信の審査に通りたいから、ちょっとだけ病歴を隠そうかな…」
このような考えは絶対に持たないでください。告知義務違反は、思っている以上に重大なリスクを伴います。
告知義務違反とは何か
告知義務違反とは、団信の告知書で:
- 故意に事実を記入しない
- 事実と異なる内容を記入する
などの行為を指します。「ちょっとくらい…」と思って告知しなかった病気が、後々大きなトラブルになることもあるんです。
告知義務違反のリスク
告知義務違反が発覚した場合、以下のようなリスクがあります:
- 保険契約の解除: 団信の契約が解除され、保障が受けられなくなります
- 保険金不払い: 万が一の際に保険金が支払われず、ローン残高が残ったままとなります
- ローンの一括返済要求: 金融機関によっては、住宅ローンの一括返済を求められることも
- 家を失うリスク: 一括返済ができない場合、最悪の場合は家を手放さなければならない可能性も
「そんな…」と思われるかもしれませんが、実際にこのようなケースは発生しています。一時的に審査に通ったとしても、長い目で見れば家族を守れなくなってしま
