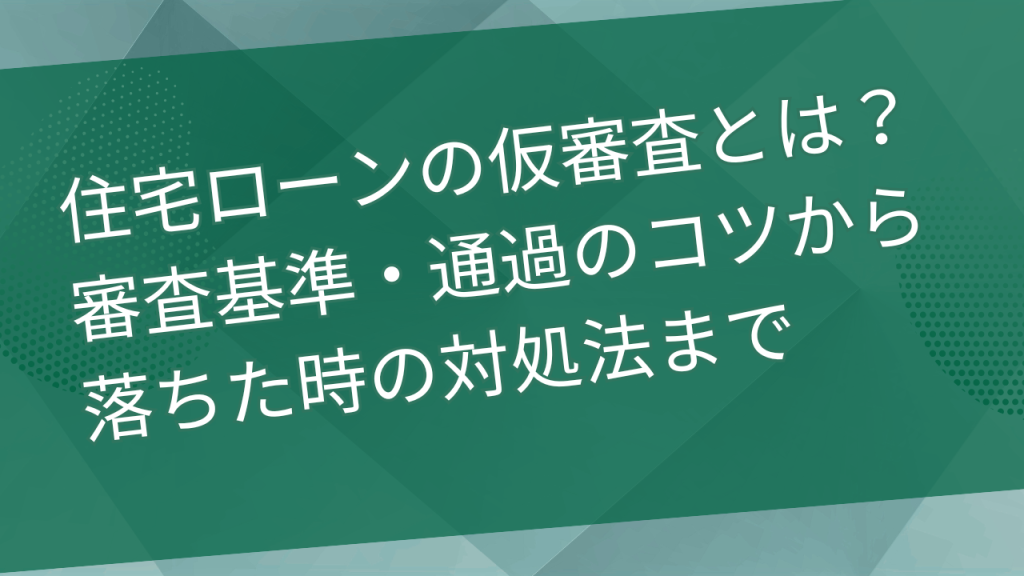
マイホーム購入を検討しているあなた、「住宅ローンの仮審査って何?」「どうやったら通過できるの?」と不安を感じていませんか?
住宅ローンは人生で最も大きな借り入れになることが多く、その第一関門となるのが「仮審査(事前審査)」です。この審査をクリアしなければ、せっかく見つけた理想の物件を手に入れることができません。
本記事では、住宅ローンの仮審査について徹底解説します。審査の流れや基準から必要書類、通過のコツ、さらには審査に落ちてしまった場合の対処法まで、マイホーム購入を成功させるために知っておくべき情報をすべて網羅しています。
これからマイホームを買おうとしている方はもちろん、将来的に購入を考えている方も、ぜひ参考にしてください!
住宅ローンを簡単に比較してあなたにぴったりの金利の安い銀行が探せる!
モゲチェックだけの優遇金利でお得に借りよう!
↓↓↓↓↓
目次
住宅ローン仮審査(事前審査)とは?
住宅ローン仮審査とは、正式な審査(本審査)の前に行われる予備審査のことです。金融機関によって「仮審査」または「事前審査」と呼び方が異なることがありますが、意味は同じです。
この仮審査は、あなたが希望する金額の住宅ローンを借りられる可能性があるかどうかを、簡易的に判断するプロセスです。本審査前に行うことで、本審査で否決されるリスクを減らし、マイホーム購入をスムーズに進めることができます。
仮審査と本審査の違い
住宅ローンの審査は「仮審査」と「本審査」の2段階で行われるのが一般的です。では、この2つはどのように異なるのでしょうか?
| 項目 | 仮審査(事前審査) | 本審査 |
|---|---|---|
| 審査内容 | 利用者自身の返済能力を中心に審査 | 返済能力に加え、購入物件の担保価値や健康状態も詳細に確認 |
| 必要書類 | 本人確認書類や収入証明書類など基本的な書類 | 仮審査の書類に加え、物件関係書類など多岐にわたる |
| 審査期間 | 数日〜1週間程度 | 1週間〜4週間程度 |
| 申込タイミング | 物件購入申込と同時期が多い | 不動産売買契約締結後 |
仮審査は本審査に比べて簡易的なチェックですが、だからといって軽視してはいけません。なぜなら、仮審査に通過しなければ本審査を受けることができないからです。
また、仮審査は複数の金融機関に申し込むことができます。実際、条件比較のためにいくつかの金融機関に同時に申し込む人も多いですよ。特にネット銀行では即日〜翌日に結果が出ることもあるので、比較検討がしやすいというメリットがあります。
住宅ローン仮審査のメリット
- 本格的な住宅購入前に融資可能性が確認できる
- 複数の金融機関に申し込み、条件を比較できる
- 融資可能額が明確になり、予算に合った物件選びができる
- 本審査に比べて必要書類が少なく、手続きが簡単
次に、住宅ローン審査の全体的な流れを見ていきましょう。
住宅ローン審査の流れとタイミング
マイホーム購入を成功させるためには、住宅ローン審査の流れを理解し、適切なタイミングで行動することが重要です。ここでは、住宅ローンの審査から融資実行までの一般的な流れを詳しく解説します。
1. 仮審査(事前審査)の申し込み
物件の購入申し込みを行うのとほぼ同時期に、希望する金融機関に仮審査を申し込みます。この段階では、本人確認書類や収入証明書類などの基本的な書類を提出します。
最近はネット銀行をはじめとして、インターネット上で簡単に申し込みができる金融機関も増えています。中には、仮審査の段階では書類提出が不要で、オンライン上での入力のみで申し込める場合もありますよ。
2. 仮審査結果の通知
仮審査の結果は、通常数日から1週間程度で通知されます。ネット銀行の場合は、早ければ即日〜翌日に結果が出ることもあります。
結果が「承認」であれば、次のステップに進むことができます。この段階で、融資可能額や金利の概要も伝えられます。「否決」の場合は、残念ながらその金融機関からの住宅ローン融資は難しいことになります。
3. 不動産売買契約の締結
仮審査に通過したら、不動産会社と売買契約を締結します。この際、「ローン特約」を付けることが一般的です。これは、後の本審査で住宅ローンが通らなかった場合に、ペナルティなしで契約を解除できる条項です。
実は、建売一戸建てや中古住宅の購入の場合、購入申し込み後に仮審査が通るまで売主に契約を待ってもらう「仮押さえ」をするケースも多いんです。ただ、売主によっては仮押さえの期間が短く、仮審査の結果が間に合わないこともあるので注意が必要です。
4. 本審査の申し込み
売買契約締結後、正式に住宅ローンの申し込み(本審査)を行います。本審査では仮審査より多くの書類が必要となり、物件関係書類(売買契約書、重要事項説明書など)なども提出します。
5. 本審査
本審査では、仮審査よりも詳細な審査が行われます。申込者の返済能力に加え、物件の担保価値や健康状態も細かくチェックされます。
本審査の結果が出るまでには、1〜4週間ほどかかるのが一般的です。金融機関によっては、本店と支店が協力して二重チェックを行うなど、慎重に審査を進めるため時間がかかることもあります。
6. 住宅ローン契約の締結
本審査に通過すると、正式な住宅ローン契約を締結します。この段階で、住宅ローンの金利タイプ(変動金利や固定金利)、適用金利、借入額、返済期間、返済方法などが確定します。
最近では、住宅ローンの電子契約を活用する金融機関も増えていますが、契約書類はしっかり確認し、控えを保管しておくことが大切です。
7. 団体信用生命保険(団信)への加入
住宅ローン契約時には、多くの金融機関で団体信用生命保険(団信)への加入が必須となります。これは、ローン返済中に契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、残りのローン残債が保険金で返済される仕組みです。
団信に加入するには健康状態の告知が必要で、健康状態によっては加入が難しいケースもあります。その場合、通常の団信より加入条件の緩い「ワイド団信」が提供されていることもあります。
8. 融資実行と引き渡し
すべての手続きが完了すると、融資実行日(引き渡し日)に以下のことが行われます:
- 住宅ローンの融資実行(銀行口座に融資金が入金)
- 売主への残金決済
- 諸費用などの支払い
- 所有権移転登記
- 抵当権設定登記
- 書類や鍵の受け取り(引き渡し)
引き渡しは通常、司法書士が同席した上で住宅ローンを契約した金融機関で行われます。これで晴れてマイホームのオーナーになれます!
注意ポイント
仮審査から融資実行までの期間中は、転職や新たな借り入れなど、審査に影響を与える可能性のある行動は避けるべきです。もし状況に変化がある場合は、必ず担当者に相談しましょう。
ここまで住宅ローン審査の全体的な流れを見てきました。次に、仮審査で具体的に何がチェックされるのか、審査基準について詳しく見ていきましょう。
仮審査の審査基準 – 何がチェックされる?
住宅ローンの仮審査では、あなたの返済能力や信用状態が主にチェックされます。国土交通省の調査によると、多くの金融機関が重視している審査項目は以下の通りです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 完済時年齢(98.5%の金融機関が審査項目に挙げている)
完済時年齢は、住宅ローンを完済する予定の年齢のことです。多くの金融機関では、完済時年齢の上限を80歳未満に設定しています。
例えば、あなたが現在40歳で35年ローンを組む場合、完済時年齢は75歳となります。これは上限の80歳未満なので問題ありませんが、50歳で35年ローンを希望すると完済時年齢は85歳となり、審査で不利になる可能性があります。
完済時年齢が高い場合は、借入期間を短くする、頭金を増やして借入額を減らすといった対策が考えられます。
2. 健康状態(96.6%)
住宅ローンを利用するには、多くの場合「団体信用生命保険(団信)」への加入が必須です。そのため、団信に加入できる健康状態であることが重要な審査項目となります。
特に持病がある場合や過去に大きな病気を経験している場合は注意が必要です。団信の審査で問題になりそうな場合は、事前に金融機関に相談し、加入条件の緩い「ワイド団信」があるか確認するとよいでしょう。ただし、ワイド団信を利用すると金利が0.2〜0.3%程度上乗せされることが多いので、返済額が増えることも考慮する必要があります。
3. 借入時年齢(96.0%)
借入時の年齢も重要な審査項目です。多くの金融機関では、借入時年齢の上限を65歳未満または70歳未満に設定しています。
これは定年退職後の収入減少を考慮したものです。もし定年後も安定した収入がある場合は、その証明ができれば審査で有利になる可能性があります。
4. 年収(94.0%)
安定した返済を続けるためには、十分な収入が必要です。金融機関によって最低年収基準は異なりますが、多くは年収150万円以上を条件としています。ただし、金融機関によっては100万円以上、200万円以上、250万円以上などさまざまです。
また、パートやアルバイト、契約社員の場合は、正社員よりも厳しく審査される傾向があります。勤続年数や雇用の安定性も重要な判断材料になります。
5. 勤続年数(93.6%)
勤続年数は、現在の仕事をどれだけ長く続けているかを示す指標で、雇用の安定性をチェックするために重視されます。
一般的に、正社員の場合は勤続3年以上が望ましいとされています。転職して間もない場合や、個人事業主・フリーランスとして独立して間もない場合は、審査で不利になることがあります。
個人事業主やフリーランスの場合は、3年分の確定申告書を提出して安定した収入があることを証明できると良いでしょう。
6. 返済負担率(92.0%)
返済負担率とは「年収に占める年間のローン返済額の割合」のことです。住宅ローンの返済額だけでなく、自動車ローンや教育ローン、カードローンなど、すべての借り入れの返済額を合計して計算されます。
多くの金融機関では、返済負担率の上限を年収の30〜45%程度に設定していますが、実際に無理なく返済を続けるためには25%以内に抑えることがおすすめです。
例えば、年収500万円の場合、返済負担率25%だと年間の返済額は125万円、月々では約10.4万円が目安となります。
返済負担率の計算例
年収500万円の人が返済負担率を25%以内に抑える場合:
500万円 ÷ 12ヶ月 × 25% = 約10.4万円/月
つまり、月々の返済額は約10.4万円以内に設定するのが望ましいでしょう。
7. 担保評価(91.8%)
購入する不動産(住宅)は、住宅ローンの担保となります。そのため、物件が融資額に見合う価値を持っているかどうかも重要な審査項目です。
担保評価は、土地と建物の登記簿謄本などの資料をもとに行われます。特に中古物件の場合は、築年数や立地条件によって担保価値が大きく変わることがあるため注意が必要です。
8. 信用情報
返済能力と並んで重要なのが、あなたの信用情報です。過去のローンやクレジットカードの支払い履歴などが記録された「個人信用情報」が審査対象となります。
延滞や債務整理の記録があると、いわゆる「ブラックリスト」に掲載されていると見なされ、審査に大きく影響します。特に、クレジットカードの支払い遅延や携帯電話料金の滞納など、意外と気づかないうちに信用情報に傷がついていることもあるので注意が必要です。
信用情報の傷は、原因によって5〜10年ほど記録が残ります。少額でも返済の遅延があると、住宅ローンの審査に悪影響を与える可能性があるので、日頃から支払いは確実に行いましょう。
信用情報に傷がつく主な原因
- クレジットカードの支払い遅延
- 携帯電話やスマホの分割払い(クレジット)の滞納
- カードローンやキャッシングの返済遅延
- 公共料金のクレジット払いの滞納
- 奨学金の返済遅延
- 過去の債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)
これらの審査基準を踏まえ、次は仮審査に必要な書類について詳しく見ていきましょう。
仮審査に必要な書類リスト
仮審査を申し込む際には、いくつかの書類を提出する必要があります。必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的に以下のような書類が求められます。事前に準備しておくことで、審査をスムーズに進めることができますよ。
1. 本人確認書類
まずは、あなたが誰であるかを確認するための書類です。以下のいずれかを準備しましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(表面のみ。裏面のマイナンバーは提出不要の場合が多い)
- パスポート(住所の記載があるもの)
- 健康保険証
外国籍の方の場合は、以下の書類も必要です:
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民票謄本(マイナンバー記載なし)
※いずれも有効期限内のものを用意してください。
2. 収入証明書類
あなたの収入を証明するための書類です。雇用形態によって必要な書類が異なります。
会社員・公務員の場合:
- 源泉徴収票(直近のもの)
- 給与明細書(直近3ヶ月分)
- 賞与明細書(直近2回分、ある場合)
個人事業主・自営業の場合:
- 確定申告書(直近2〜3年分)
- 所得税の納税証明書(その1、その2)
- 決算報告書(法人の場合)
金融機関によっては、仮審査の段階では収入証明書類の提出が不要で、正式申し込み(本審査)の際に提出するよう案内されることもあります。
3. 物件資料
購入予定の物件に関する資料です。物件によって必要書類が異なります。
新築一戸建て・マンションの場合:
- 物件のパンフレットやチラシ
- 建築会社や不動産会社からの見積書
- 工事請負契約書(契約済みの場合)
- 土地の所在地が分かる資料
中古住宅・マンションの場合:
- 物件の広告やチラシ
- 土地と建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 売買契約書(契約済みの場合)
- 建物の間取り図や図面
物件がまだ決まっていない段階での仮審査の場合、物件資料は不要のことが多いです。その場合は、おおよその購入予定額や希望エリアなどを申告することになります。
4. その他必要な書類
状況によっては、以下のような書類も必要になります:
- 他のローンの返済予定表(自動車ローン、教育ローンなど返済中のローンがある場合)
- 住宅ローン控除証明書(住宅ローンの借り換えの場合)
- 健康診断結果(金融機関から求められた場合)
- 戸籍謄本(配偶者と収入合算する場合など)
最近の傾向:オンライン申込と電子提出
近年では、特にネット銀行を中心に、仮審査はオンラインで申し込み、必要書類もスマホで撮影してアップロードするだけでOKというケースが増えています。また、仮審査の段階では書類提出が不要で、本審査の際にまとめて提出するというパターンもあります。申込先の金融機関の案内にしたがって対応しましょう。
必要書類が揃ったら、次は仮審査に通るためのポイントについて見ていきましょう。
仮審査に通るためのポイント・対策
住宅ローンの仮審査をスムーズに通過するためには、事前の準備と対策が欠かせません。ここでは、元銀行員やファイナンシャルプランナーのアドバイスをもとに、仮審査通過率を高めるためのポイントを紹介します。
1. 家計の洗い出しと健全化
まずは自分の家計状況をしっかり把握することが重要です。特に以下の点に注目して整理しましょう。
- 年収と手取り収入の把握:安定した収入があることを証明できるようにしましょう。
- 現在の借入状況の確認:自動車ローン、教育ローン、カードローンなど、すべての借り入れを洗い出します。
- 返済計画表の作成:現在の借入がいつ完済するのかを把握し、返済計画を立てましょう。
家計の状況を事前に把握しておくことで、自分がどの程度の住宅ローンを借りられるかの目安がわかります。また、仮審査の際に既存の借り入れについて質問されても、きちんと答えられるようになりますよ。
住宅ローン借入可能額の目安
一般的な目安として、「年収の5〜6倍程度」と言われていますが、これはあくまで目安です。より正確には、返済負担率から逆算して考えるとよいでしょう。
例:年収500万円、返済負担率25%、金利1.0%、35年返済の場合
月々の返済可能額 = 500万円÷12ヶ月×25% = 約10.4万円
借入可能額の目安 = 約3,500万円
2. 返済や支払いの履歴を管理する
信用情報に傷がつかないよう、日頃から以下の点に注意しましょう:
- クレジットカードの支払いは必ず期日までに:1回の遅延でも信用情報に記録されます。
- 携帯電話やスマホの料金支払いに注意:分割払いで購入している場合は特に注意が必要です。
- 公共料金もクレジットカード払いの場合は注意:口座残高不足で引き落としができないと、信用情報に傷がつく可能性があります。
- 奨学金の返済は確実に:奨学金の返済遅延も信用情報に影響します。
信用情報の記録は5〜10年残るため、住宅ローンを検討する数年前から注意して管理することが理想的です。
3. 住宅購入前の大きな買い物は控える
マイホーム購入を控えている時期は、他の大きな買い物は避けるのが賢明です。特に以下の点に注意しましょう。
- 自動車などの高額商品のローン購入を避ける:返済負担率に影響します。
- 新規のクレジットカード作成や枠の増額を控える:キャッシング枠は利用していなくても借入枠として審査に影響することがあります。
- 家具や家電などの購入は住宅ローン契約後に:新居用の家具購入も、住宅ローン契約が完了してからにしましょう。
マイホームが決まると、「新居に置く家具や家電を早く買いたい!」という気持ちになりますが、まずは住宅ローンの契約が完了するまで待つことが大切です。特に分割払いでの購入は要注意です。
4. 健康管理をしっかり行う
住宅ローンを組むには、多くの場合団体信用生命保険(団信)への加入が必須です。健康上の問題で団信に加入できないと、住宅ローン自体が組めなくなる可能性があります。
- 定期的な健康診断を受ける:早期発見・早期治療が重要です。
- 持病がある場合は事前に相談:金融機関によっては、条件付きで対応してくれることもあります。
- ワイド団信の検討:通常の団信に入れない場合、条件の緩いワイド団信の利用も考えましょう。
病歴がある場合は、事前に複数の金融機関に相談し、対応可能な金融機関を探すことも一つの方法です。フラット35は団信加入が必須ではないため、選択肢に入れておくとよいでしょう。
5. キャリアプランと住宅購入のタイミングを調整する
転職や独立のタイミングと住宅購入のタイミングは慎重に考えましょう。
- 転職は住宅購入の前か後に:転職直後は安定した収入を証明しにくいため、審査が厳しくなります。
- 独立・起業は住宅購入後に:個人事業主になると、安定した収入の証明に3年程度の実績が求められることが多いです。
- 雇用形態の変更にも注意:正社員から契約社員やパートへの変更も審査に影響します。
金融機関では、安定して長期間返済が続けられる人かどうかを重視します。勤続年数が短いと審査で不利になるため、転職や独立を考えている場合は、そのタイミングと住宅購入のタイミングを慎重に計画しましょう。
6. 複数の金融機関に申し込む
仮審査は複数の金融機関に同時に申し込むことができます。金融機関によって審査基準や金利が異なるため、比較検討することをおすすめします。
- 3〜4社程度に申し込む:条件の異なる金融機関を選びましょう。
- メガバンク、地方銀行、ネット銀行など種類を分ける:審査基準が異なる場合があります。
- 住宅ローン専門の金融機関も検討:柔軟な対応が期待できることもあります。
ただし、申し込みすぎると審査担当者に「あちこちで断られている」という印象を与える可能性もあるため、申込先は厳選しましょう。また、ネット銀行の中には即日〜翌日に結果が出るところもあるので、最初にそういった金融機関に申し込み、結果を見てから次の行動を決めるのも効率的です。
仮審査通過のための6つのポイント
- 家計の洗い出しと健全化を行う
- 返済や支払いの履歴を管理する
- 住宅購入前の大きな買い物は控える
- 健康管理をしっかり行う
- キャリアプランと住宅購入のタイミングを調整する
- 複数の金融機関に申し込み、比較検討する
このようなポイントに注意して準備を進めれば、仮審査に通過する確率はぐっと高まります。しかし、残念ながら仮審査に落ちてしまうこともあります。次は、仮審査に落ちる理由とその対処法について見ていきましょう。
仮審査に落ちる理由とその対処法
住宅ローンの仮審査に落ちてしまった場合、理由を把握して適切に対処することが大切です。ここでは、仮審査に落ちる主な理由と、それぞれの対処法について詳しく解説します。
仮審査に落ちる主な理由
1. 信用情報に傷がある
最も多い理由のひとつが、過去のローンやクレジットカードの支払い遅延など、信用情報に問題がある場合です。
- クレジットカードの支払い延滞:たった1回の延滞でも記録に残ります。
- 携帯電話料金の未払い:分割払いで購入したスマホの支払い遅延も影響します。
- 奨学金の返済遅れ:教育ローンの延滞も記録されます。
- 過去の債務整理:任意整理、個人再生、自己破産などの記録は長期間残ります。
これらの信用情報の傷は、種類によって5〜10年程度記録が残ります。特に自己破産の記録は10年近く残るため、その間は住宅ローンの審査が厳しくなります。
2. 返済負担率が高すぎる
年収に対して借入希望額が大きすぎる、または他のローンも含めた返済負担が大きい場合も、仮審査に通らない原因となります。
- 年収に対して希望借入額が多い:年収の5〜6倍を超える借入は厳しく見られることが多いです。
- 他のローンの返済額が多い:自動車ローン、教育ローン、カードローンなどの返済額も含めた総返済負担率が高い。
- キャッシング枠の存在:使っていなくても、クレジットカードのキャッシング枠が借入枠としてカウントされることも。
返済負担率の目安は年収の30〜35%以内ですが、他のローンの返済額も含めて計算されることを忘れないでください。
3. 基本的な条件をクリアしていない
金融機関が設定している基本条件に合致していないケースもあります。
- 最低年収に満たない:金融機関によって150万円以上、200万円以上など基準が異なります。
- 勤続年数が短い:転職直後や独立間もない場合は、安定収入の証明が難しいと判断されることも。
- 完済時年齢が上限を超えている:多くの金融機関では完済時80歳未満が条件です。
これらの基本条件は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
4. 健康状態に問題がある
団体信用生命保険(団信)に加入できない健康状態の場合、住宅ローンの審査に通らないことがあります。
- 持病や既往症がある:特にがんや心臓病、脳疾患などの既往歴がある場合、団信の審査が厳しくなります。
- 健康診断で異常が指摘されている:健康診断の結果が団信の審査に影響することも。
健康上の理由で団信に加入できない場合でも、ワイド団信の利用や、団信加入が必須ではないフラット35などの選択肢があります。
仮審査に落ちた場合の対処法
仮審査に落ちてしまっても、諦める必要はありません。理由を特定し、適切に対処することで再チャレンジできます。
1. 落ちた理由を確認する
まずは、なぜ仮審査に落ちたのかを把握することが大切です。
- 金融機関の担当者に聞いてみる:審査内容の詳細は教えてもらえないことが多いですが、返済負担率の問題なのか、信用情報の問題なのかなど、大まかな理由を教えてくれることもあります。
- 自分の信用情報を確認する:個人信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)に開示請求して、自分の信用情報を確認できます。
理由がわかれば、次のステップで適切な対処法を選べます。
2. 条件を変更して再申込みする
返済負担率の問題であれば、借入条件を見直すことで対応できる場合があります。
- 借入希望額を減らす:頭金を増やすか、少し予算を下げた物件を検討しましょう。
- 返済期間を調整する:返済期間を短くすると月々の返済額は増えますが、完済時年齢の問題を解決できることも。
- 収入合算を検討する:配偶者の収入も合わせることで、返済能力をアピールできます。
条件変更後、同じ金融機関に再申込みする場合は、前回の審査から3〜6ヶ月程度空けるのが一般的です。
3. 他のローンを完済する
他のローンが返済負担の原因となっている場合は、それらを整理することも検討しましょう。
- 自動車ローンなどを繰り上げ返済する:親からの援助や貯蓄を活用して完済できれば、返済負担率が改善します。
- カードローンを完済する:返済中のカードローンがあれば、完済を優先しましょう。
- 不要なクレジットカードを解約する:キャッシング枠が設定されているカードは、使っていなくても借入枠としてカウントされることがあります。
ただし、住宅ローン審査の直前にカードを解約すると、かえって不審に思われることもあるので、時期には注意が必要です。
4. 別の金融機関に申し込む
金融機関によって審査基準は異なるため、別の金融機関であれば審査に通る可能性もあります。
- 金融機関の種類を変える:メガバンクから地方銀行、ネット銀行、信用金庫など、種類の異なる金融機関を試してみましょう。
- 住宅ローン専門金融機関を検討する:住宅ローンに特化した金融機関は、柔軟な審査基準を持っていることもあります。
- フラット35の利用を検討する:団信加入が必須ではなく、長期固定金利型住宅ローンとして人気があります。
ただし、短期間に多数の金融機関に申し込むと、「あちこちで断られている」と判断される恐れがあるため、申込先は慎重に選びましょう。
5. 時間をかけて根本的な解決を図る
すぐに解決できない問題の場合は、時間をかけて根本的な対策を講じることも必要です。
- 収入を増やす:転職やスキルアップで年収アップを目指します。
- 勤続年数を伸ばす:転職直後の場合は、しばらく同じ職場で実績を積みましょう。
- 信用情報の回復を待つ:信用情報の傷は時間の経過とともに消えていくので、それまで待つことも選択肢です。
今すぐ住宅を購入できなくても、長期的な視点で計画を立て直すことで、将来的にはより良い条件でマイホームを手に入れられるかもしれません。
危険なサービスには注意!
「審査に通らなくても住宅ローンを組める」「信用情報に問題があっても大丈夫」といった怪しい広告やサービスには絶対に手を出さないでください。悪質な業者に騙されるリスクがあります。住宅ローンは正規の金融機関で、正当な手続きを踏んで組むのが安全です。
仮審査に落ちてしまっても、原因を特定し適切に対処すれば、いずれ住宅ローンを組むことは可能です。焦らず、計画的に進めていきましょう。
次は、住宅ローンの審査期間を短縮するポイントについて見ていきます。
審査期間を短縮するポイント
住宅ローンの審査はできるだけスムーズに進めたいものです。特に物件の購入を検討している段階では、審査結果が出るまでの時間が気になりますよね。ここでは、審査期間を短縮するためのポイントを紹介します。
1. 提出書類の不備をなくす
審査をスムーズに進めるもっとも基本的なポイントは、提出書類に不備がないようにすることです。
- 必要書類は漏れなく準備する:事前に必要書類リストを確認し、すべてそろえておきましょう。
- 記入漏れや誤記入をチェックする:申込書の記入内容に誤りがないか、署名や捺印が必要な箇所は漏れていないかを確認します。
- 有効期限が切れていないか確認する:運転免許証やパスポートなどの有効期限をチェックしましょう。
書類に不備があると、再提出を求められ、その分審査が遅れることになります。特に郵送でのやり取りが必要な場合は、往復の時間も考慮すると大幅な遅延につながります。
2. 事前に必要書類を準備しておく
物件が決まる前から、必要な書類を準備しておくと、いざというときにスムーズに申し込めます。
- 収入証明書類を準備する:源泉徴収票や確定申告書などは、年度更新されるため、常に最新のものを手元に置いておくと便利です。
- 本人確認書類を更新しておく:運転免許証やパスポートの有効期限が近い場合は、更新しておきましょう。
- 他のローンの返済予定表を用意する:自動車ローンなど、返済中のローンがある場合は、返済予定表を取り寄せておきます。
事前準備をしておくことで、物件が決まったらすぐに仮審査の申し込みができ、時間短縮につながります。
3. 繁忙期を避ける
住宅ローンの申込みには繁忙期があります。この時期は申込件数が多く、審査に時間がかかりやすいので注意しましょう。
- 1〜3月は特に混雑:新学期や転勤シーズンに合わせた住み替えが多く、不動産取引が活発になります。
- 月末は審査が集中しやすい:月末に審査が集中する傾向があります。
- 金利優遇キャンペーン中も混雑:特別金利キャンペーンを実施している時期は申込みが増えます。
可能であれば、4〜6月や10〜11月など、比較的空いている時期を狙うと審査がスムーズに進みやすいでしょう。
4. ネット銀行を選ぶ
審査のスピードを重視するなら、ネット銀行の住宅ローンも検討する価値があります。
- 仮審査のスピードが速い:ネット銀行の仮審査は最短で翌日、場合によっては即日で結果が出ることもあります。
- 24時間いつでも申込可能:店舗の営業時間を気にせず、好きな時間に申し込めます。
- オンラインでの書類提出:スマホで撮影してアップロードするだけで書類提出できるため、郵送の手間と時間を省けます。
ただし、ネット銀行でも本審査の期間は従来型の銀行と大きく変わらないことが多いです。また、ネットでの手続きに不安がある方は、サポート体制が充実している従来型の銀行のほうが安心できるかもしれません。
5. 審査担当者と良好な関係を築く
従来型の銀行で申し込む場合は、担当者とのコミュニケーションも重要です。
- 質問には迅速に回答する:担当者からの問い合わせには速やかに対応しましょう。
- 誠実な態度で接する:隠し事をせず、正直に状況を伝えることが大切です。
- 追加書類の提出は早めに:追加書類を求められたら、できるだけ早く提出しましょう。
担当者と良好な関係を築くことで、スムーズな手続きが期待できます。ただし、審査そのものを左右するわけではないので、過度な期待は禁物です。
6. 信用情報を事前に確認しておく
審査が長引く原因のひとつに、信用情報の問題があります。事前に自分の信用情報をチェックしておくと安心です。
- JICCやCICなどで信用情報を確認:個人信用情報機関に開示請求することで、自分の信用情報を確認できます。
- 問題があれば事前に対処:返済遅延などの記録があれば、まずはその問題を解決しておきましょう。
- 不明な記録があれば問い合わせる:身に覚えのない記録があれば、信用情報機関に問い合わせて確認することも可能です。
信用情報に問題があると、審査に時間がかかるだけでなく、否決される可能性も高まります。事前に確認して対処しておくことが大切です。
信用情報の開示請求方法
主な個人信用情報機関は以下の3つです。それぞれのウェブサイトから開示請求が可能です。
- JICC(日本信用情報機構)
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- JBA(全国銀行個人信用情報センター)
開示にはいずれも1,000円程度の手数料がかかりますが、自分の信用情報を知るための投資と考えるとよいでしょう。
審査期間を短縮するためのポイントを押さえ、計画的に住宅ローンの申込みを進めましょう。次は、仮審査に関するよくある質問にお答えします。
仮審査に関するよくある質問
住宅ローンの仮審査について、多くの方が疑問を持つポイントをQ&A形式でまとめました。マイホーム購入を成功させるために、ぜひ参考にしてください。
Q1: 仮審査の申し込みは複数の金融機関に行っても大丈夫?
A: はい、問題ありません。むしろ、複数の金融機関に申し込んで比較検討することをおすすめします。金融機関によって審査基準や金利条件が異なるため、3〜4社程度に申し込むことで、より良い条件を見つけられる可能性が高まります。
ただし、短期間に多数の金融機関(10社以上など)に申し込むと、「あちこちで断られている」と判断される恐れがあるため、申込先は厳選したほうが良いでしょう。また、異なるタイプの金融機関(メガバンク、地方銀行、信用金庫、ネット銀行など)を選ぶと、幅広い選択肢を得られます。
Q2: 仮審査に通っても本審査に落ちることはある?
A: あります。仮審査と本審査では確認項目や審査の厳密さが異なるため、仮審査に通過しても本審査で否決される可能性はあります。主な理由としては以下が考えられます:
- 仮審査の申告内容と実際の条件に相違があった:年収や勤続年数などを誤って申告していた場合
- 本審査までの間に状況が変化した:転職や退職、新たな借り入れがあった場合
- 物件の担保価値に問題があった:購入予定物件の担保評価が低かった場合
- 健康状態で団信に加入できなかった:健康告知で問題が見つかった場合
本審査で否決されるリスクを減らすためには、仮審査で正確な情報を申告し、本審査までの間に状況を変えないことが大切です。また、購入予定の物件についても、築年数や立地条件など担保価値に影響する要素をしっかりチェックしておきましょう。
Q3: 個人信用情報を自分で確認したい場合、どうすればいい?
A: 個人信用情報は、以下の3つの信用情報機関で確認できます:
- JICC(日本信用情報機構):消費者金融やクレジット会社の情報が多く登録されています。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジットカード会社の情報が多く登録されています。
- JBA(全国銀行個人信用情報センター):銀行などの金融機関の情報が多く登録されています。
開示請求の方法は、各機関のウェブサイトから行う方法、郵送で申し込む方法、窓口で直接申し込む方法があります。それぞれ1,000円程度の手数料がかかりますが、自分の信用情報を正確に把握するための重要な投資と考えるとよいでしょう。
なお、自分で信用情報を照会しても、信用情報に傷がつくことはありません。安心して確認してください。
Q4: 新規借入と借り換えでは審査基準が異なる?
A: 基本的な審査項目は同じですが、借り換えの場合は以下の点で異なる傾向があります:
- 返済実績が評価される:現在の住宅ローンを滞りなく返済していれば、信用度の高さとしてプラス評価されます。
- 勤続年数の重要度が低い:すでに住宅ローンを返済している実績があれば、転職後間もない場合でも比較的柔軟に対応してもらえることがあります。
- 借入金額が物件価値を超えない:借り換えでは物件の現在価値を超える借入はできないため、追加融資を希望する場合は注意が必要です。
ただし、借り換え時に健康状態が悪化していたり、年収が大幅に下がっていたりすると、新規借入時よりも条件が厳しくなることもあります。特に団信の審査は、年齢が上がるにつれて厳しくなる傾向があるので注意が必要です。
Q5: 住宅ローンの事前審査は何歳までに受けるべき?
A: 年齢そのものより、「完済時年齢」が重要です。多くの金融機関では、完済時年齢を80歳未満に設定しているため、例えば35年ローンを組む場合は45歳までに、30年ローンなら50歳までに、というように逆算して考えるとよいでしょう。
ただし、年齢が高くなるほど健康リスクも高まるため、団信の加入条件が厳しくなる傾向があります。また、高齢になるにつれて融資条件が厳しくなったり、金利が上乗せされたりすることもあります。
そのため、できるだけ若いうちにマイホーム購入を検討するのが有利であることは間違いありません。ただし、条件や金融機関によっては、定年後も返済可能な収入が見込める場合には柔軟に対応してもらえることもあるので、あきらめずに相談してみるとよいでしょう。
Q6: 審査期間が長引いている理由は?
A: 審査期間が予想より長引く場合、以下のような理由が考えられます:
- 繁忙期で審査件数が多い:1〜3月などは特に混雑します。
- 提出書類に不備がある:記入漏れや添付忘れがあると確認に時間がかかります。
- 追加資料の提出を求められている:特殊な条件の案件は追加書類が必要になることがあります。
- 信用情報に確認事項がある:過去の支払い遅延などの記録があると確認に時間がかかります。
- 詳細な審査が必要と判断された:借入希望額が高額、年収に対する返済額が大きい、自営業者の場合などは時間がかかります。
審査が長引いている場合は、金融機関の担当者に状況を確認してみるとよいでしょう。追加書類が必要な場合は速やかに対応し、審査をスムーズに進められるようにしましょう。
Q7: フリーランスや自営業でも住宅ローンは組める?
A: はい、フリーランスや自営業でも住宅ローンを組むことは可能です。ただし、会社員に比べると審査条件は厳しくなる傾向があります。主なポイントは以下の通りです:
- 安定した収入の証明が必要:最低でも2〜3年分の確定申告書や納税証明書が必要です。
- 事業の継続性が評価される:長く同じ仕事を続けていると有利です。
- 青色申告が望ましい:白色申告よりも青色申告のほうが審査で有利になります。
- 適正な所得の申告:経費を過大に計上して所得を抑えていると、返済能力の評価が下がります。
フリーランスや自営業の場合は、フラット35や、自営業者向けの住宅ローン商品を扱う金融機関を検討するのも一つの方法です。また、取引実績のある金融機関や、専門家(ファイナンシャルプランナーや住宅ローン専門家)に相談するのもおすすめです。
Q8: 住宅ローンの仮審査は何回でも受けられる?
A: 基本的に回数制限はありませんが、短期間に同じ金融機関で何度も申し込むと、審査に悪影響を与える可能性があります。一般的には、条件が大きく変わらない限り、同じ金融機関での再申込みは3〜6ヶ月ほど間を空けることが望ましいでしょう。
また、複数の金融機関に同時に申し込むことは問題ありませんが、あまりにも多くの金融機関に申し込むと、「あちこちで断られている」と判断されるリスクがあります。3〜4社程度が適切な数と言えるでしょう。
仮審査に落ちた場合は、なぜ落ちたのかを把握し、条件を改善してから再チャレンジするのが効果的です。例えば、借入希望額を減らす、頭金を増やす、返済期間を短くするなどの対策を講じてから再申込みすると、通過確率が上がります。
仮審査に関するよくある質問まとめ
- 複数の金融機関への申込みはOK(3〜4社が目安)
- 仮審査通過でも本審査で否決される可能性はある
- 個人信用情報は専門機関で自分でも確認できる
- 借り換えでは返済実績が評価されることがある
- 完済時年齢は80歳未満が目安
- フリーランス・自営業でも条件を満たせば借入可能
- 同じ金融機関での再申込みは3〜6ヶ月の間隔を開けるのが望ましい
住宅ローンの仮審査に関する疑問点が解消されたでしょうか?最後に、これまでの内容をまとめて、マイホーム購入を成功させるための重要ポイントを確認しましょう。
まとめ:住宅ローン仮審査を成功させるために
この記事では、住宅ローンの仮審査(事前審査)について詳しく解説してきました。マイホーム購入の第一関門である仮審査を通過するためには、以下のポイントをしっかり押さえておくことが重要です。
仮審査の基本を理解しよう
- 仮審査と本審査の違いを把握する:仮審査は簡易的な審査で、主に返済能力を中心にチェック。本審査ではさらに詳細な審査が行われます。
- 審査の流れとタイミングを理解する:物件購入申込と同時期に仮審査を申し込み、結果は数日~1週間程度で出ることが多い。
- 審査基準を把握する:完済時年齢、健康状態、年収、返済負担率、信用情報などが主な審査項目です。
仮審査に向けた準備を徹底しよう
- 必要書類を事前に準備する:本人確認書類、収入証明書類、物件資料など、必要書類を漏れなく用意しましょう。
- 家計の現状を把握する:収入、支出、借入状況を整理し、どの程度の住宅ローンを組めるか事前に試算しておきましょう。
- 信用情報をチェックする:過去の支払い遅延などが記録されていないか、自分の信用情報を確認しておきましょう。
仮審査通過のためのポイントを押さえよう
- 返済や支払いの履歴を管理する:クレジットカードの支払いなど、すべての支払いを確実に行い、信用情報に傷をつけないようにしましょう。
- 大きな買い物は控える:住宅購入前には車などの高額商品の購入は避け、他のローンを組まないようにしましょう。
- 健康管理に気を配る:団信に加入できる健康状態を維持することも重要です。
- 転職や独立のタイミングに注意する:転職直後や独立間もない時期は審査が厳しくなるため、住宅購入のタイミングを調整しましょう。
- 複数の金融機関に申し込む:審査基準は金融機関によって異なるため、比較検討することが大切です。
仮審査に落ちた場合でも諦めないで
- 落ちた理由を確認する:信用情報の問題か、返済負担率の問題かなど、原因を特定しましょう。
- 条件を見直す:借入希望額を減らす、頭金を増やす、返済期間を調整するなど、条件を変更して再チャレンジしましょう。
- 他のローンを整理する:他の借入が原因なら、それらを完済することも検討しましょう。
- 別の金融機関を試す:審査基準は金融機関によって異なります。他の選択肢も検討しましょう。
- 時間をかけて根本的な解決を:収入を増やす、勤続年数を伸ばすなど、長期的な視点で対策を講じましょう。
住宅ローンは人生で最も大きな借り入れになることが多く、返済期間も長期にわたります。そのため、無理のない返済計画を立て、将来の生活に支障をきたさないようにすることが何よりも重要です。
適切な準備と計画的なアプローチで、仮審査を通過し、マイホーム購入の夢を実現させましょう!もし不安なことがあれば、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することもおすすめです。彼らの知識と経験があなたのマイホーム購入を強力にサポートしてくれるはずです。
