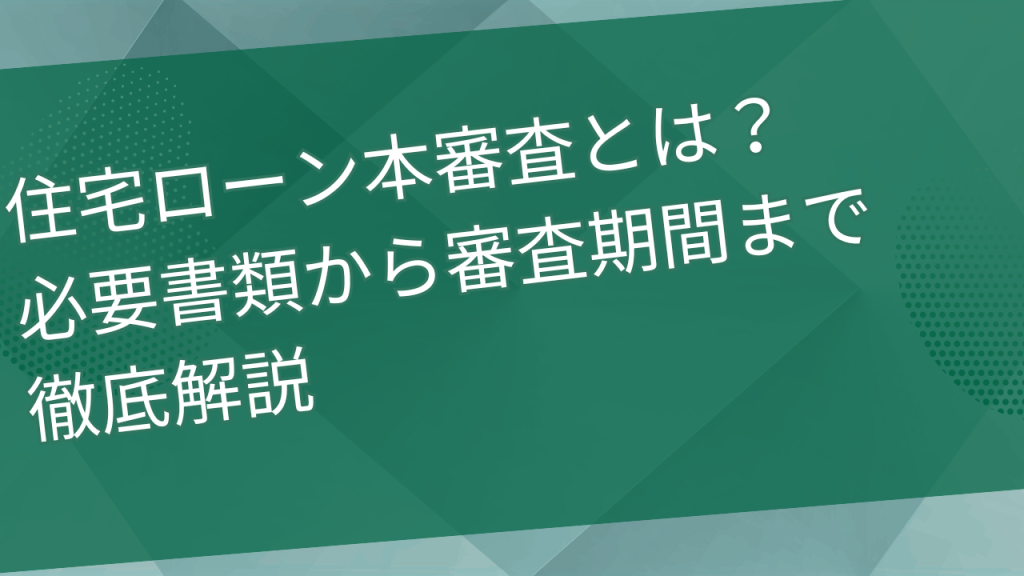
マイホーム購入の夢を実現するためには避けて通れない「住宅ローンの本審査」。事前審査は通過したけれど、本審査はもっと厳しいと聞いて不安になっている方も多いのではないでしょうか?
実際、住宅ローンの本審査は事前審査よりも詳細で厳密な審査が行われます。そして何より怖いのは、「事前審査に通ったのに本審査で落ちてしまった」というケースも少なくないということ。
今回は、住宅ローンの本審査について徹底解説します。必要な書類や審査のポイント、本審査から融資実行までの流れ、そして審査に落ちないためのコツまで、あなたがマイホームを手に入れるために必要な情報をすべてまとめました。
これから住宅ローンを申し込む方はもちろん、すでに事前審査を通過し本審査を控えている方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
住宅ローンを簡単に比較してあなたにぴったりの金利の安い銀行が探せる!
モゲチェックだけの優遇金利でお得に借りよう!
↓↓↓↓↓
目次
事前審査と本審査の違いとは?
「事前審査に通ったのに、なぜまた本審査があるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。実は、この2つの審査には明確な違いがあります。
事前審査(仮審査)の目的と特徴
事前審査は、その名の通り「事前に」あなたが住宅ローンを借りられる可能性があるかどうかを簡易的に判断するものです。主に以下のポイントが特徴です。
事前審査のポイント:
- 申込者が申告した情報(年収や借入希望額など)をもとに審査
- 書類提出が少ない、または不要な場合も
- 結果が早い(最短即日〜1週間程度)
- 複数の金融機関に同時に申し込み可能
- 審査に通過しても借入れの義務はない
事前審査の段階では、具体的な物件が決まっていないケースもあります。そのため、あくまでも「このくらいの金額なら貸せる可能性がある」という見込みを示すに過ぎません。
また、事前審査は比較的簡易な審査のため、複数の金融機関に同時に申し込んで金利や融資条件を比較検討することもできます。これは、最適な住宅ローンを選ぶ上で非常に重要なポイントですね。
本審査(正式審査)の目的と特徴
一方、本審査は住宅ローンを正式に申し込む段階で行われる詳細な審査です。ここでは事前審査よりも厳密に、あなたの返済能力や物件価値などを精査します。
本審査のポイント:
- 提出書類が多く、すべて正確であることが求められる
- 申告内容だけでなく、実際の書類による裏付けが重視される
- 物件の担保価値も詳細に評価される
- 審査期間が長い(1〜3週間が一般的、長いと1ヶ月以上)
- 審査通過後は実際に契約に進むことが前提
本審査では、事前審査で申告した内容と提出書類の内容に相違がないかも厳しくチェックされます。例えば、年収を実際より高く申告していたり、他の借入れを隠していたりすると、それだけで審査落ちの原因になります。
また、購入する物件自体の価値も重要な審査ポイントになります。物件が担保としての価値が低いと判断されると、借入額が制限されたり、最悪の場合は審査が通らなくなる可能性もあります。
なぜ2段階の審査が必要なのか?
ここで疑問に思うのは「なぜ2回も審査があるのか?」ということですよね。
これには大きく2つの理由があります。
1つ目は、住宅ローンが非常に高額であり、長期間の契約になるためです。数千万円という大金を数十年という長い期間で貸し出すわけですから、金融機関としては慎重に審査する必要があります。
2つ目は、不動産取引のタイミングの問題です。物件を購入するためには売主と契約を結ぶ必要がありますが、そのためには「住宅ローンが借りられるかどうか」があらかじめわかっていないと困りますよね。かといって、物件が決まる前に詳細な審査をするのも難しいのです。
そこで、まず簡易的な事前審査で借入れの見込みを立て、物件が決まってから詳細な本審査を行うという2段階の審査が一般的になっているわけです。
このように、事前審査と本審査はそれぞれ異なる目的と役割を持っています。特に本審査は住宅ローン契約に直結する重要な審査ですので、しっかりと準備して臨むことが大切です。
住宅ローン本審査の期間はどれくらい?
住宅ローンの本審査にかかる期間は、申込者の状況や金融機関によって異なりますが、一般的には以下のような目安があります。
一般的な審査期間の目安
住宅ローンの本審査は、書類をすべて提出してから結果が出るまで、一般的に1〜3週間程度かかります。ただし、金融機関や審査内容によっては、4週間以上かかるケースもあります。
例えば、メガバンクや地方銀行の場合は、本店と支店での二重チェックや保証会社との連携があるため、審査期間が長くなる傾向があります。一方、ネット銀行では審査システムの効率化により、比較的早く結果が出ることが多いようです。
以下に、金融機関のタイプ別に一般的な審査期間の目安を示します:
メガバンク・地方銀行:約2〜3週間(長いと4週間以上)
ネット銀行:約1〜2週間
信用金庫・JA:約2〜3週間
ただし、これはあくまでも目安であり、個人の状況や申込み内容、金融機関の繁忙期などによって大きく変わることがあります。
審査期間が長引く要因
本審査の期間が予想以上に長引く場合、以下のような要因が考えられます。
1. 提出書類の不備
必要書類が不足していたり、記載内容に誤りがあったりすると、金融機関から修正や追加書類の提出を求められます。これにより審査期間が長引くことがあります。
2. 審査内容の複雑さ
以下のような場合、審査がより複雑になり、時間がかかることがあります:
- 自営業者など、収入が安定していない場合
- 借入額が年収に対して大きい場合
- 他の借入れが多い場合
- 信用情報に問題がある場合
3. 金融機関の繁忙期
不動産取引が活発になる1〜3月(年度末)や9〜10月(秋の引っ越しシーズン)などは、住宅ローンの申込み件数も増えるため、審査に時間がかかることがあります。
4. 物件の特殊性
購入する物件が古い、特殊な構造である、立地条件に問題があるなど、担保評価が難しい場合は、審査に時間がかかることがあります。
金融機関別の特徴
金融機関のタイプによっても、審査期間や特徴には違いがあります。
メガバンク・地方銀行
対面での相談や手続きが基本となるため、来店予約や書類のやり取りに時間がかかることがあります。また、本審査は本部での審査が必要なため、支店との連携によっても時間が左右されます。
最近では、事前審査のWeb申込みや一部手続きのオンライン化を進めている銀行も増えていますが、本審査における書類提出や契約手続きは依然として店頭での対応が基本となっています。
ネット銀行
ネット銀行の最大の特徴は、24時間いつでもオンラインで手続きができることです。来店不要で手続きが完結するため、時間的な制約が少ないのが魅力です。
また、AIを活用した審査システムの導入により、審査のスピードも比較的早い傾向にあります。ただし、書類の提出は郵送やアップロードによって行うため、その点は従来型の銀行と大きな違いはありません。
信用金庫・JA
地域密着型の金融機関として、地元の不動産事情に詳しいというメリットがあります。審査基準が柔軟な場合もありますが、一般的には審査期間はメガバンクと同程度かそれ以上かかることが多いです。
審査期間を考慮したスケジュール管理
住宅購入のスケジュールを立てる際には、本審査にかかる期間を十分に考慮する必要があります。特に、物件の引き渡し日や住み替えのタイミングに合わせるためには、余裕をもったスケジュール管理が重要です。
一般的には、事前審査から本審査、契約、融資実行までトータルで1〜2ヶ月、長い場合は3ヶ月程度の期間を見込んでおくと安心です。また、年度末などの繁忙期を避けて申し込むことで、審査期間を短縮できる可能性もあります。
実際に申し込む際には、各金融機関の審査期間の目安について、事前に確認しておくことをおすすめします。また、不動産業者や住宅メーカーとも連携しながら、全体のスケジュールを調整していくことが大切です。
本審査に必要な書類一覧
住宅ローンの本審査では、事前審査よりも多くの書類が必要になります。金融機関によって多少の違いはありますが、基本的には以下のような書類が求められます。ここでは、カテゴリー別に必要書類を詳しく解説します。
本人確認に関する書類
まずは、申込者本人であることを証明するための書類です。
1. 本人確認書類(以下のいずれか)
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーが記載されている裏面は提出不要の場合が多い)
- 在留カード(外国籍の場合)
2. 健康保険証
健康保険証は単なる本人確認だけでなく、勤務先の規模や勤続年数を確認できるため、審査において重要視されます。社会保険の種類(健康保険組合、協会けんぽなど)から勤務先の安定性が推測されるためです。
3. 住民票
住民票は、同居する家族構成や続柄を確認するために必要です。以下の点に注意してください。
- 世帯全員が記載されたもの(個人のみの住民票では不可)
- 続柄が明記されているもの
- 発行後3ヶ月以内のもの
- マイナンバーの記載がないもの(マイナンバーが必要な場合は金融機関から別途指示があります)
4. 印鑑証明書と実印
金融機関によっては、契約時に印鑑証明書と実印が必要になります。印鑑証明書も住民票と同様、発行後3ヶ月以内のものが求められます。
収入に関する書類
次に、申込者の返済能力を判断するための収入証明書類です。これは雇用形態や職業によって異なります。
1. 給与所得者(会社員・公務員など)の場合
■ 源泉徴収票
直近1年分(または2年分)が必要です。転職した場合は、前職の源泉徴収票も求められることがあります。
■ 住民税決定通知書または課税証明書
源泉徴収票に加えて、住民税決定通知書(勤務先から受け取るもの)または課税証明書(市区町村で発行)が必要な場合もあります。
■ 給与明細書
源泉徴収票がない場合や、最近昇給した場合などは、直近3ヶ月分程度の給与明細書の提出を求められることがあります。
2. 自営業者・フリーランスの場合
■ 確定申告書
直近2〜3年分の確定申告書(第一表・第二表)と、所得税青色申告決算書または収支内訳書が必要です。電子申告(e-Tax)の場合は、受付日時等が印字された「受信通知」や「メール詳細」も一緒に提出します。
■ 納税証明書(その1・その2)
所得金額と納税状況を証明する書類です。税務署で発行され、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
■ 事業に関する書類
事業の実態を証明するため、以下のような書類が追加で必要になることもあります。
- 営業許可証や免許証のコピー
- 事務所や店舗の賃貸借契約書
- 確定申告書の内容を補足する帳簿や売上台帳など
3. 会社経営者・役員の場合
■ 会社の決算書
直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書など)が必要です。
■ 法人税の納税証明書
会社が適正に納税していることを示す書類です。
■ 役員報酬が確認できる書類
源泉徴収票や給与明細書など、個人としての収入が確認できる書類も必要です。
物件に関する書類
住宅ローンの対象となる物件に関する書類も重要です。物件の種類や購入方法によって必要書類が異なります。
1. 新築・中古物件購入の場合(共通)
■ 不動産売買契約書
売買契約書の全ページのコピーが必要です。
■ 重要事項説明書
物件の法的状況や制限などが記載された書類です。こちらも全ページ必要です。
■ 物件パンフレット・価格表
特に売買契約前の場合、物件の間取りや価格が確認できる資料が必要です。
2. 土地購入・注文住宅建築の場合(追加書類)
■ 工事請負契約書
建築会社との契約書のコピーです。変更契約がある場合はその書類も必要です。
■ 建築確認申請書・建築確認済証
建築基準法に適合していることを示す書類です。
■ 見積書
工事代金の詳細が記載されたものが必要です。
3. 中古物件購入・リフォームの場合(追加書類)
■ リフォーム工事請負契約書または見積書
リフォーム工事の内容と金額が確認できる書類です。
4. 登記に関する書類
■ 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
物件の権利関係を確認するための書類です。売主から提供されるか、自分で法務局から取得します。
その他の状況に応じて必要となる書類
申込者の状況によって、以下のような追加書類が必要になることもあります。
1. 住宅ローン以外の借入れがある場合
■ 返済予定表・借入残高証明書
他のローン(自動車ローン、教育ローン、カードローンなど)の借入状況を確認するための書類です。
2. 転職して間もない場合
■ 職歴書
転職して3年未満の場合、過去の職歴を記載した書類が必要になることがあります。
■ 雇用契約書
新しい職場での雇用条件を確認するための書類です。
3. 団体信用生命保険に加入する場合
■ 健康診断結果証明書
年齢や借入額によっては、健康状態を確認するための健康診断書が必要になることがあります。
4. 収入合算や連帯保証人がいる場合
配偶者などと収入を合算して申し込む場合や、連帯保証人を立てる場合は、その人の本人確認書類や収入証明書類なども必要です。
書類準備の際の注意点
住宅ローンの本審査に必要な書類を準備する際は、以下の点に注意しましょう。
1. 有効期限を確認する
住民票や印鑑証明書、納税証明書などの公的書類には有効期限があります。多くの場合、発行後3ヶ月以内のものが求められますので、申込みのタイミングに合わせて取得しましょう。
2. 正確な情報を提供する
事前審査時に申告した内容と、本審査で提出する書類の内容に相違があると、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。特に年収や借入状況については、正確な情報を提供することが重要です。
3. 余裕をもって準備する
書類の取得には時間がかかることがあります。特に役所や税務署で発行される書類は、混雑状況によっては即日発行できないこともあります。余裕をもって準備しましょう。
4. コピーは鮮明に
書類のコピーを提出する場合は、文字や数字が鮮明に読み取れることを確認してください。特にFAXやスマートフォンで撮影した画像は不鮮明になりがちですので注意が必要です。
5. 原本とコピーの区別に注意する
どの書類が原本で、どの書類がコピーで良いのかを事前に確認しておきましょう。特に公的書類は原本が必要なケースが多いです。
必要書類は金融機関によって異なる場合がありますので、申し込む前に必ず確認するようにしましょう。また、不明な点があれば、遠慮せずに金融機関の担当者に質問することが大切です。
本審査で重視されるチェックポイント
住宅ローンの本審査では、申込者の返済能力や担保となる物件の価値など、さまざまな角度からチェックが行われます。ここでは、金融機関が特に重視する主なポイントについて解説します。
返済能力に関するチェックポイント
1. 年収と返済負担率
年収に対する返済負担率(年間の返済額÷年収)は、最も重視される指標の一つです。金融機関によって基準は異なりますが、一般的には以下のような目安があります。
- 年収400万円未満:返済負担率25%程度まで
- 年収400〜700万円:返済負担率30%程度まで
- 年収700万円以上:返済負担率35%程度まで
返済負担率が高すぎると、「この収入で本当に返済していけるのか」という疑念から審査が厳しくなります。また、この計算では既存の借入れ(カーローンや奨学金など)も含めた総返済額が対象となるため、他の借入れが多いと住宅ローンの借入可能額が制限されることになります。
2. 雇用形態と勤続年数
安定した収入があるかどうかも重要な審査ポイントです。一般的に、正社員として長く勤めている人のほうが審査で有利になります。
- 正社員:最も安定した雇用形態として評価されます
- 契約社員・派遣社員:契約期間や更新実績などをチェックされます
- パート・アルバイト:勤続年数が長いほど評価されます
- 自営業・フリーランス:最低でも2〜3年の事業実績が求められることが多いです
勤続年数についても、長いほど評価は高くなります。一般的には、現在の勤務先での勤続年数が3年以上あると安定していると判断されます。転職して間もない場合は、前職の勤続年数も含めて総合的に判断されることが多いです。
3. 勤務先の業種や規模
勤務先の安定性も審査の重要なポイントです。公務員や大企業の社員は、中小企業の社員よりも雇用が安定していると判断される傾向にあります。また、業種によっても評価が異なり、景気の影響を受けにくい業種(インフラ、医療、教育など)は比較的高く評価されます。
4. 他の借入れ状況
住宅ローン以外の借入れ(カーローン、教育ローン、カードローン、クレジットカードのリボ払いなど)も、返済能力を判断する重要な要素です。特に、複数の借入れがある場合や、カードローンの利用限度額が高額に設定されている場合は、住宅ローンの審査に影響することがあります。
5. 年齢と完済時年齢
借入時の年齢と完済時の年齢も重要なチェックポイントです。多くの金融機関では、完済時の年齢が80歳未満であることを条件としています。そのため、年齢が高い申込者の場合、返済期間が短くなり、その分、毎月の返済額が高くなるため、返済負担率の面でも厳しい審査になることがあります。
担保(物件)に関するチェックポイント
1. 物件の担保評価
住宅ローンでは、購入する物件に対して抵当権が設定され、その物件が担保となります。金融機関は、万が一返済が滞った場合に物件を売却して回収できるかどうかを重視します。
物件の担保評価額(金融機関が設定する物件の価値)は、実際の購入価格とは異なる場合があります。一般的に、以下のような要素が評価に影響します。
- 物件の立地条件(駅からの距離、周辺環境など)
- 物件の築年数(新しいほど評価は高くなる)
- 物件の構造(鉄筋コンクリート造、木造など)
- 物件の規模や間取り
- 物件の状態(リフォームの有無など)
担保評価が低すぎると、希望する借入額が認められないこともあります。
2. 物件の法的な制限
物件に法的な制限がある場合、担保価値が下がる可能性があります。例えば、以下のような条件は審査に影響します。
- 再建築不可物件
- 接道義務を満たしていない物件
- 建築基準法に適合していない物件
- 土地の権利が借地権の物件
3. 物件の将来性
物件の将来的な価値も重要な要素です。例えば、過疎化が進む地域や、災害リスクが高い地域にある物件は、将来的な価値の下落が懸念されるため、審査が厳しくなる可能性があります。
信用情報に関するチェックポイント
1. 個人信用情報
過去の借入れや返済状況は、個人信用情報機関に記録されています。金融機関は、これらの信用情報をチェックして、申込者の信用度を判断します。
特に以下のような項目が重視されます。
- 過去の返済遅延の有無
- 債務整理やクレジットカードの強制解約の有無
- 短期間での複数の借入申込みの有無
個人信用情報に問題があると、住宅ローンの審査に大きな影響を与えます。例えば、過去に返済遅延があると、その情報は5〜10年程度記録されており、その間は住宅ローンの審査が厳しくなる可能性があります。
2. 税金や社会保険料の滞納
税金(所得税、住民税など)や社会保険料の滞納も、返済能力や信用度を判断する重要な要素です。特に、住民税の滞納があると、課税証明書にその旨が記載されるため、審査に悪影響を及ぼします。
その他のチェックポイント
1. 健康状態
住宅ローンでは、一般的に団体信用生命保険への加入が条件となります。これは、借入者が死亡や高度障害状態になった場合に、保険金で住宅ローンの残債が返済される仕組みです。
そのため、健康状態も審査の重要なポイントとなります。持病がある場合や、健康診断で異常が見つかった場合は、保険の引受条件が厳しくなり、結果として住宅ローンの審査にも影響する可能性があります。
2. 頭金の割合
物件価格に対する頭金の割合も、審査の判断材料となります。頭金が多いほど、借入額が少なくなるため、返済負担が軽減され、審査が通りやすくなる傾向があります。一般的には、物件価格の2割程度の頭金があると良いとされています。
3. 家族構成
家族構成も審査に影響することがあります。例えば、共働き世帯や、将来的に家族が増える可能性がある若い夫婦などは、収入増加や安定した生活基盤という観点から、プラスに評価されることがあります。
4. 金融資産
預貯金などの金融資産も、返済能力を補完する要素として評価されます。特に、自己資金(頭金)以外にも余裕資金がある場合は、万が一の際の返済原資として考慮されることがあります。
これらのチェックポイントは、金融機関によって重視する度合いが異なります。また、一つのポイントだけで審査結果が決まるわけではなく、総合的に判断されるものです。自分の状況を客観的に評価し、不安な点があれば事前に対策を講じておくことが大切です。
本審査に落ちる主な理由とその対策
住宅ローンの事前審査に通過したからといって、本審査に必ず通過するわけではありません。ここでは、本審査に落ちる主な理由と、それぞれの対策について解説します。
書類の不備・不足
落ちる理由:
本審査で最も多い否決理由の一つが、提出書類の不備や不足です。具体的には以下のようなケースが考えられます。
- 必要書類の提出漏れ
- 書類の有効期限切れ(住民票や印鑑証明書など)
- 書類の内容に誤りや矛盾がある
- 記入漏れや押印漏れ
特に深刻なのは、事前審査で申告した内容と本審査で提出した書類の内容に相違がある場合です。例えば、年収を実際より高く申告していたり、他の借入れを隠していたりすると、信用問題となり審査に落ちる可能性が高くなります。
対策:
- 必要書類のリストを事前に確認し、漏れなく準備する
- 公的書類(住民票、印鑑証明書など)は発行日をチェックし、有効期限内のものを用意する
- 申込書などの記入内容は、事前審査時の申告内容と一致させる
- 記入もれや押印もれがないか、提出前に再確認する
- 不明な点は、遠慮せずに金融機関の担当者に質問する
収入や返済能力に関する問題
落ちる理由:
収入が少なすぎる、または借入希望額に対して返済能力が不足していると判断された場合、審査に落ちる可能性があります。
- 年収に対して借入希望額が大きすぎる
- 返済負担率が高すぎる(他の借入れも含めて)
- 収入の安定性に不安がある(非正規雇用、勤続年数が短いなど)
- 転職直後で収入の継続性が確認できない
対策:
- 借入希望額を年収に見合った適正な金額に抑える
- 他の借入れがある場合は、可能であれば事前に完済しておく
- 収入合算(配偶者の収入も合わせて申し込む)を検討する
- 頭金を増やして借入額を減らす
- 返済期間を長くして月々の返済額を抑える(ただし、金利負担は増える)
信用情報の問題
落ちる理由:
過去の借入れや返済状況に問題があると、信用情報機関にその記録が残り、住宅ローンの審査に影響します。
- 過去に返済遅延や延滞があった
- 債務整理やクレジットカードの強制解約の履歴がある
- 税金や社会保険料の滞納がある
- 短期間に複数の借入申込みをしている
対策:
- 普段から各種支払いは必ず期日内に行う習慣をつける
- 税金や社会保険料の滞納がある場合は、速やかに完済する
- 信用情報に問題がある場合は、一定期間(5〜10年程度)経過するのを待つ
- 住宅ローン申込み前の短期間に、複数のローンやクレジットカードの申込みをしない
物件(担保)に関する問題
落ちる理由:
購入する物件に問題があると、担保としての価値が低くなり、審査に影響します。
- 物件の担保評価額が購入価格よりも大幅に低い
- 築年数が古すぎる物件
- 再建築不可物件などの法的制限がある物件
- 狭小地や変形地などの特殊な土地
- 災害リスクが高い地域にある物件
対策:
- 担保評価が高くなりやすい物件を選ぶ(駅近、新築・築浅、標準的な間取りなど)
- 物件の法的制限や特殊性については、事前に不動産会社や金融機関に確認する
- 担保評価が低い物件の場合は、頭金を多めに用意する
- 場合によっては、担保評価が高い別の物件に変更することも検討する
審査中の状況変化
落ちる理由:
事前審査から本審査までの間に、申込者の状況が変わってしまうと、審査に影響することがあります。
- 事前審査後に新たな借入れをした
- 転職や退職をした
- 家族構成や健康状態に変化があった
対策:
- 住宅ローンの審査中は、新たな借入れを極力避ける
- 審査中の転職は避け、転職を考えている場合は住宅ローン契約後に行う
- 状況に変化があった場合は、速やかに金融機関に相談する
団体信用生命保険の加入条件に満たない
落ちる理由:
住宅ローンでは、一般的に団体信用生命保険への加入が条件となりますが、健康上の理由で加入できないと、住宅ローン自体も利用できないことがあります。
- 持病や既往症がある
- 健康診断で異常が見つかった
- 年齢が高すぎる
対策:
- 持病がある場合は、事前に団信加入の可否を確認する
- 通常の団信に加入できない場合は、引受条件が緩和された団信特約を検討する
- 団信なしでも住宅ローンを提供している金融機関を探す(ただし金利が高くなる傾向がある)
本審査に落ちた場合の対応策
もし本審査に落ちてしまった場合は、以下のような対応策を検討しましょう。
1. 落ちた理由を確認する
まずは、金融機関に審査に落ちた理由を確認します。プライバシーの観点から詳細な理由を教えてもらえないこともありますが、大まかな理由(収入面、物件面、信用面など)を聞くことで、次の対策を立てることができます。
2. 条件を見直して再申込みする
審査に落ちた理由に応じて、以下のような条件を見直し、同じ金融機関または別の金融機関に再申込みすることも検討できます。
- 借入額を減らす(頭金を増やす)
- 返済期間を調整する
- 収入合算を検討する
- 連帯保証人を立てる
3. 別の金融機関を検討する
金融機関によって審査基準は異なります。特に、以下のような金融機関は、審査基準が比較的緩やかな場合があります。
- 地方銀行や信用金庫(特に地元密着型の金融機関)
- フラット35(財形住宅融資)
- 審査基準の緩い住宅ローン商品を提供している金融機関
4. 住宅購入計画を見直す
場合によっては、物件選びから見直すことも必要です。例えば、以下のような選択肢を検討しましょう。
- 価格帯を下げた物件を探す
- 担保評価が高くなりやすい物件(駅近、新築など)を選ぶ
- 住宅購入自体を延期し、収入アップや借入れ返済などに努める
住宅ローンの本審査に落ちることは決して珍しいことではありません。大切なのは、原因を把握して適切な対策を講じることです。焦らず計画的に進めることで、マイホームの夢を実現させましょう。
本審査通過後の流れ:契約から融資実行まで
住宅ローンの本審査に無事通過したら、次は契約手続きと融資実行のステップに進みます。ここでは、本審査通過後から実際に住宅ローンを借り入れて物件を取得するまでの流れを詳しく解説します。
金銭消費貸借契約(本契約)
1. 契約内容の確定
本審査通過後、まずは住宅ローンの詳細な契約内容が確定します。主な確定事項は以下の通りです。
- 借入金額:物件価格から頭金を引いた金額(諸費用込みの場合もあり)
- 金利タイプ:変動金利、固定金利、固定期間選択型など
- 適用金利:契約時点での金利
- 返済期間:何年ローンにするか
- 返済方法:元利均等返済、元金均等返済など
- 返済日:毎月の返済日(銀行によって固定の場合と選択可能な場合あり)
- ボーナス返済:有無と金額
- 繰上返済の条件:手数料や最低金額など
この段階で、金利タイプやボーナス返済の有無など、選択できる項目については最終決定します。金利については、申込時よりも下がっていれば、下がった金利が適用されることが一般的です。
2. 契約書類の作成と契約手続き
契約内容が確定すると、金融機関は契約書類を作成します。主な契約書類は以下の通りです。
- 金銭消費貸借契約書
- 抵当権設定契約書
- 団体信用生命保険申込書
- 約定書(誓約書)
- 各種同意書
契約手続きは、金融機関の店頭で行うのが一般的ですが、最近ではインターネットバンキングを通じて電子契約ができる金融機関も増えています。
店頭での契約の場合は、契約者本人が来店し、実印での押印や本人確認が必要です。電子契約の場合は、電子署名や本人確認のための認証手続きが必要になります。
3. 契約時に必要な費用
住宅ローン契約時には、以下のような費用が必要になることがあります。
- 事務手数料:融資額の2.2%程度が一般的
- 印紙税:契約書に貼付する収入印紙代
- 保証料:保証会社を利用する場合(一括払いかローンに上乗せするかを選択できる場合が多い)
- 火災保険料:金融機関指定の火災保険に加入する必要がある場合
これらの費用は、金融機関や契約内容によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
融資実行の準備
契約が完了すると、融資実行に向けた準備が始まります。この段階では、主に以下のような手続きが行われます。
1. 抵当権設定の準備
住宅ローンでは、購入する物件に金融機関のために抵当権を設定します。これは、万が一返済ができなくなった場合に、金融機関がその物件を売却して債権を回収するための法的な権利です。
抵当権設定の手続きは、通常、司法書士が代行します。必要書類の準備や登記申請の手続きを行います。
2. 融資実行日の調整
融資実行日(借入日)は、物件の引き渡し日に合わせて設定されます。通常、売主、買主(契約者)、不動産会社、金融機関の間で日程調整が行われます。
融資実行日が決まったら、金融機関から融資実行日の通知や、当日の手続き内容についての案内がありますので、内容をよく確認しておきましょう。
3. 返済用口座の準備
住宅ローンの返済は、通常、金融機関の指定する口座からの自動引き落としで行われます。契約した金融機関に口座を持っていない場合は、新たに口座を開設する必要があります。また、引き落とし日に残高不足にならないよう、返済計画を立てておくことも大切です。
融資実行と物件の引き渡し
いよいよ融資実行日を迎えます。この日には、以下のような手続きが一度に行われることが一般的です。
1. 融資金の入金
契約した金融機関から、契約者の指定口座に融資金が入金されます。この入金を確認してから、物件代金の支払いが行われます。
2. 物件代金の決済
融資金と頭金を合わせて物件代金を売主に支払います。この際、不動産会社や司法書士が立ち会って、取引の安全を確保します。
また、仲介手数料や登記費用などの諸費用の支払いも、この段階で行われることが多いです。
3. 物件の引き渡し
代金の決済が完了すると、売主から鍵が引き渡され、物件の所有権があなたに移転します。これにより、晴れてマイホームの所有者となります。
4. 各種登記手続き
物件の引き渡しと同時に、以下の登記手続きが行われます。
- 所有権移転登記:物件の所有者があなたになったことを登記します
- 抵当権設定登記:金融機関のために抵当権を設定する登記を行います
これらの登記手続きは、通常、司法書士が代行します。登記が完了すると、後日、登記簿謄本(登記事項証明書)が送付されますので、内容を確認して大切に保管しておきましょう。
返済開始
融資実行後、所定の返済日から住宅ローンの返済が始まります。返済開始のタイミングは以下のようになります。
1. 初回返済日
初回の返済日は、融資実行日から1〜2ヶ月後に設定されることが一般的です。例えば、毎月26日が返済日の場合、5月10日に融資実行されたならば、初回返済日は6月26日または7月26日となります。
2. 返済額の確認
初回の返済額は、通常の月々の返済額と異なる場合があります。これは、融資実行日から初回返済日までの期間(端数期間)の利息が上乗せされるためです。契約時に返済予定表が交付されますので、初回返済額と2回目以降の返済額をよく確認しておきましょう。
3. 返済管理
住宅ローンの返済は長期間にわたります。返済計画を立てて、計画的に返済していくことが大切です。また、以下のような点にも注意しましょう。
- 返済日前に口座残高を確認し、残高不足にならないようにする
- ボーナス返済がある場合は、ボーナス返済月の返済額に注意する
- 繰上返済を検討する場合は、条件や手数料を確認する
- 金利が変動する場合は、返済額の変更に備える
これで、住宅ローンの本審査から融資実行、返済開始までの一連の流れが完了します。マイホームを手に入れた喜びとともに、計画的な返済を心がけて、快適な住生活を送りましょう。
本審査をスムーズに進めるための実践的アドバイス
住宅ローンの本審査をスムーズに進めるためには、事前の準備と適切な対応が不可欠です。ここでは、審査期間を短縮し、審査結果を有利にするための実践的なアドバイスを紹介します。
書類準備を効率的に行うためのポイント
1. 必要書類リストを作成する
まず、申し込む金融機関の必要書類リストを入手し、自分専用のチェックリストを作成しましょう。このリストには、以下の項目を含めると便利です。
- 書類の名称
- 入手方法・入手先
- 有効期限の有無と期限日
- 入手状況(未・手配中・入手済)
- 提出状況(未・提出済)
2. 書類を効率的に集める順序を考える
書類によっては、入手に時間がかかるものがあります。特に役所や勤務先で発行される書類は、手続きに時間がかかる場合があるため、早めに手配しましょう。
効率的な書類収集の順序例:
- 勤務先発行の書類(源泉徴収票、住民税決定通知書など)→ 発行に時間がかかる場合がある
- 役所発行の書類(住民票、印鑑証明書、課税証明書など)→ 平日
