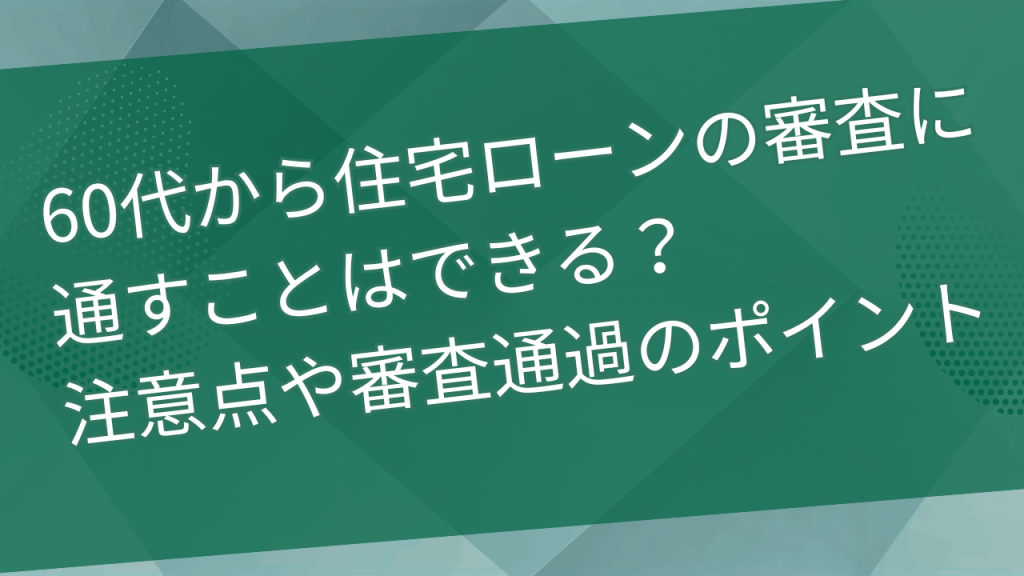
「60歳を過ぎたけどマイホームを持ちたい」
そう考えている方は意外と多いものです。子育ても一段落し、ようやくゆとりができた頃に「終の棲家」として新居を構えたいと思うのは自然なことです。しかし、60代での住宅ローンは審査に通りにくいと言われています。
実際、多くの金融機関では年齢制限を設けており、60代からの住宅ローン利用にはハードルがあるのも事実です。とはいえ、「60代だから無理」と諦めてしまうのはもったいない話。適切な対策を取れば、60代でも住宅ローンを組むことは十分可能なのです。
この記事では、60代で住宅ローン審査に通らない主な理由と、審査を通過するためのポイントを詳しく解説します。また、60代からでも活用できる住宅購入の選択肢についても紹介しますので、マイホーム購入を検討している60代の方はぜひ参考にしてください。
住宅ローンを簡単に比較してあなたにぴったりの金利の安い銀行が探せる!
モゲチェックだけの優遇金利でお得に借りよう!
↓↓↓↓↓
目次
60代で住宅ローン審査が厳しくなる5つの理由
まずは、なぜ60代になると住宅ローンの審査が厳しくなるのか、その主な理由を見ていきましょう。金融機関の審査基準を理解することで、対策も立てやすくなります。
収入の安定性と継続性に疑問符がつく
60歳といえば、多くの会社で定年退職を迎える年齢です。厚生労働省の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、70歳までの就業機会確保が努力義務とされていますが、再雇用になると収入が大幅に減るケースがほとんどです。
金融機関からすれば、「この先20年間安定して返済できる収入があるのか?」という点が最大の懸念事項になります。特に公的年金だけで返済していくことになると、返済負担率(年収に対する住宅ローン返済額の割合)が高くなりがちです。
例えば、令和5年度の夫婦二人分の標準的な年金額は月額22万4,482円(年間約269万円)。フラット35の返済負担率基準(年収400万円未満の場合は30%以下)で計算すると、月々の返済可能額は約6万7,000円が上限となります。住宅ローンだけでなく、固定資産税や修繕費などの諸経費も考えると、かなり厳しい状況です。
年齢制限に引っかかりやすい
多くの金融機関では、住宅ローンの申込時年齢上限を70歳未満、完済時年齢を80歳未満と定めています。国土交通省の調査によると、住宅ローン審査で金融機関が最も重視するのが「完済時年齢」だということがわかっています。
60歳で申し込む場合、完済時年齢が80歳という制限から、返済期間は最長でも20年に制限されます。返済期間が短くなれば月々の返済額は増えるため、返済計画の面からも厳しい審査となります。
実際のところ、完済時年齢と借入時年齢は審査項目の上位を占めており、年齢自体がネックになるケースが多いのです。
健康状態と団体信用生命保険の壁
住宅ローンを組む際には、ほとんどの場合「団体信用生命保険(団信)」への加入が必須条件となります。団信とは、ローン契約者が死亡したり高度障害になったりした場合に、残りのローンを保険金で返済する仕組みです。
60代は健康リスクが高まる年齢であり、持病がある場合や健康状態によっては団信に加入できないケースがあります。団信審査に通らなければ住宅ローンも組めないため、大きなハードルとなります。
一般の団信に加入できない場合は「ワイド団信」という引受条件が緩和された保険もありますが、保険料が高くなるなどのデメリットも生じます。
担保評価に厳しい目が向けられる
金融機関は、万が一返済が滞った場合に備えて、物件の担保価値を重視します。特に60代の場合、返済期間が短いため、物件の資産価値の減少リスクに敏感になります。
以下のような物件は担保評価が低くなりやすく、審査で不利になります。
- 築年数が経過している古い物件
- 旧耐震基準の建物
- 駅から遠いなど立地の利便性が低い物件
- 人口減少地域にある物件
特に地方の物件は、将来的な売却を想定した場合の価値下落リスクが大きいため、審査が厳しくなりがちです。
老後資金との兼ね合いが懸念される
60代は老後資金を確保すべき時期でもあります。住宅ローンの返済と老後の生活費の両立が可能かどうかも、審査では重要なポイントです。
総務省の「家計調査年報」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯では、消費支出が可処分所得を上回っており、すでに赤字の家計状況にあることがデータで示されています。このような状況で住宅ローンの返済が加わると、さらに家計が圧迫される恐れがあります。
金融機関はこうした点も考慮して、貸し倒れリスクを慎重に評価します。老後資金計画と住宅ローン返済計画の整合性も審査の対象となるのです。
住宅ローン審査で金融機関が最も重視するポイント
住宅ローンの審査では、どのような項目が重視されるのでしょうか?国土交通省住宅局の調査によると、民間金融機関が住宅ローンの融資判断で重視する上位10項目は以下の通りです。
| 順位 | 審査項目 |
|---|---|
| 1位 | 完済時年齢 |
| 2位 | 健康状態 |
| 3位 | 借入時年齢 |
| 4位 | 担保評価 |
| 5位 | 年収 |
| 6位 | 勤務先 |
| 7位 | 勤続年数 |
| 8位 | 職業 |
| 9位 | 他の借入状況 |
| 10位 | 金融資産保有状況 |
60代の申込者にとって特に注目すべきは、上位3項目がすべて年齢や健康に関連する項目だということです。完済時年齢、健康状態、借入時年齢のいずれも、60代の場合はハードルが高くなりがちです。
これらの項目は変えることができない要素ですが、担保評価(4位)や金融資産保有状況(10位)は対策を講じることができます。頭金を増やしたり、担保価値の高い物件を選んだりすることで、審査で有利になる可能性があります。
また、年収(5位)についても、公的年金だけでなく、継続的な収入源があることを示せれば、審査にプラスになります。リタイア後も何らかの収入を得る予定があるなら、その証明ができるとよいでしょう。
60代からの住宅ローン利用で考慮すべき4つのリスク
60代からの住宅ローンには、若い世代には無い特有のリスクがあります。これらのリスクを理解した上で、対策を立てることが重要です。
返済期間の短さによる毎月の負担増
前述したように、60代で住宅ローンを組む場合、完済時年齢の制限から返済期間が最長でも20年程度に制限されます。例えば、35歳で3,000万円を借りた場合と60歳で同額を借りた場合では、月々の返済額に大きな差が生じます。
住宅ローン金額3,000万円を金利1.3%、35年で借りた場合の月々返済額は約8万9,000円ですが、同じ金額を20年で返済しようとすると、月々の返済額はさらに増加します。収入が減少する時期に返済額が増えるというダブルパンチになりかねません。
東宝ハウス国分寺の試算では、60歳で住宅ローンを組み、毎月約7万円の返済をする場合でも、60歳の段階では1,000万円以上のローンが残っているという結果が出ています。退職後の収入減を考えると、この負担は小さくありません。
住宅ローンが払えなくなった時の負債リスク
もし住宅ローンの返済が滞ってしまうと、自宅を売却して残債を返済することになります。若いうちならまだ再起を図る時間がありますが、60代で住宅を失うというのは精神的にも経済的にも大きなダメージです。
特に地方など人口減少している地域では、不動産の流動性が低く、家を売却しようとしても買い手がなかなか見つからない可能性があります。仮に売却できたとしても安く買い叩かれ、住宅ローンの残債を完済できず、借金だけが残るという最悪のシナリオも考えられます。
60代で住宅を購入する場合は、いざという時のリスクヘッジを考え、売却しやすい物件選びが重要になります。
老後資金確保とのバランス問題
60代は老後の生活資金を確保すべき時期です。住宅ローンの返済と老後資金の確保を両立させるのは容易ではありません。
厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のうち、総所得に占める公的年金・恩給の割合が100%の世帯が44%、80%から100%未満の世帯が16.5%と報告されています。つまり、約6割の高齢者世帯が収入の大部分を公的年金に依存している状態です。
そのような状況で住宅ローンの支払いが加わると、生活が圧迫される恐れがあります。特に、今後医療費や介護費が増えることも見込まれる中、住宅ローンの支払いが老後生活の負担になる可能性は高いでしょう。
健康問題と介護への備え
年齢が上がるにつれて健康リスクも高まります。60代で住宅を購入しても、その後健康状態が悪化して自宅での生活が困難になるケースも考えられます。
施設入居が必要になった場合、住宅ローンの支払いと介護費用の二重負担が生じる恐れもあります。また、子どもたちから「自宅の近所に住んでほしい」「できれば一緒に暮らしてほしい」などと言われるケースもあるでしょう。
60代での住宅購入は、こうした将来的なライフスタイルの変化も視野に入れて検討する必要があります。
60代の住宅購入と住宅ローンの実態
統計データを見ると、60代の住宅購入と住宅ローンの実態が見えてきます。実際にどのような物件を購入し、どれくらいの資金を借り入れているのでしょうか。
60代の住宅購入傾向
国土交通省の「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によると、60歳以上の方が購入している物件には以下のような特徴があります。
初めて物件を購入する方(一次取得)の場合:
中古物件の購入が多い傾向にあります。住み替えではなく初めての持ち家となるケースでは、比較的リーズナブルな中古物件を選択する方が多いようです。
買い替え(二次取得)の場合:
注文住宅が55.9%、分譲集合住宅が52.6%と高い割合を占めています。これは子育てが終わり、理想の住まいへの買い替えを実現する方が多いことを示しています。
60代の住宅ローン借入状況
住宅ローン専門金融機関ARUHIの「住宅購入に関する調査2021」によると、60代の住宅ローン状況は以下のようになっています。
| 項目 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 住宅購入金額 | 約3,288万円 | 2,550万円 |
| 住宅ローン借入金額 | 約588万円 | 0円 |
| 毎月の返済額 | 約7万5,000円 | 6万円 |
| 借入期間 | 約23年 | 25年 |
注目すべきは、住宅ローン借入金額の中央値が0円という点です。中央値は全データを小さい順に並べた時の真ん中の値であり、これは60代の住宅購入者の半数以上が住宅ローンを利用せず、現金一括で購入していることを示しています。
借入れをする場合でも、平均借入額は約588万円と、住宅価格全体から見ればかなり少額です。つまり、60代の多くは退職金や貯蓄を活用し、ローン負担を最小限に抑えた住宅購入を行っているといえます。
60代で住宅ローン審査に通るための5つの対策
60代で住宅ローン審査に通るのは簡単ではありませんが、適切な対策を取れば可能性は十分にあります。以下に、審査を有利に進めるためのポイントを紹介します。
頭金を増やして借入額を減らす
退職金や貯蓄を活用して頭金を多く用意することで、借入額と返済負担を減らすことができます。頭金が多いと、金融機関からの信頼度も高まり、審査で有利になります。
ただし、老後の生活資金も必要ですので、貯蓄をすべて住宅購入に注ぎ込むのは避けるべきです。退職金の一部を頭金に充て、残りは老後資金として確保するという判断が賢明でしょう。
住宅購入時には、固定資産税や管理費、修繕積立金、さらには将来的なリフォーム費用なども考慮して、手元に十分な資金を残しておくことが大切です。
担保評価の高い物件を選ぶ
金融機関は、万が一返済が滞った場合に担保物件を売却して貸し付けた資金を回収することを想定しています。そのため、担保価値の高い物件を選ぶことは審査で有利に働きます。
担保価値が高いとされる物件の特徴は以下の通りです:
- 人口増加地域や都市部の物件
- 駅から徒歩圏内など交通の便が良い立地
- 新耐震基準を満たしている物件
- 築年数が比較的浅い物件
- 資産価値が下がりにくい人気エリアの物件
特に東京や大阪などの大都市圏の物件は資産価値が下がりにくく、リバースモーゲージなどの対象にもなりやすいため、審査でも有利になります。
複数の金融機関に申し込む
住宅ローン審査の基準は金融機関によって異なります。一つの銀行で審査に通らなくても、別の銀行では審査に通る可能性があります。
ただし、短期間に多数の申し込みをすると、信用情報機関に「住宅ローン審査中」という情報が複数記録され、かえって審査に不利になる場合もあります。3〜5社程度に絞って、計画的に申し込むのがおすすめです。
また、銀行だけでなく、信用金庫やJAバンクなど地域密着型の金融機関も検討してみましょう。地元での信用や実績を評価してもらえる可能性があります。
安定した収入源を確保・証明する
60代でも継続的な収入があることを示せれば、審査で有利になります。以下のような収入源があれば、証明書類を用意しましょう。
- 再雇用契約書や継続雇用の証明
- 年金受給証明書
- 不動産収入がある場合は賃貸契約書
- 継続的な事業収入があればその証明
- 配当金など金融資産からの安定収入
特に「高年齢者雇用安定法」の改正により、70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となっていることから、現在の勤務先で65歳または70歳まで働ける見込みがあれば、その点をアピールしましょう。
健康状態をアピールする
団体信用生命保険の審査に通ることが住宅ローン審査の大きなポイントになります。健康診断の結果が良好であれば、その証明書を用意しておくとよいでしょう。
持病があっても、適切に管理されていることが証明できれば、団信に加入できる可能性があります。必要に応じて、通院中の医師に状態を証明する診断書を書いてもらうのも一つの方法です。
一般的な団信に加入が難しい場合は、引受条件が緩和された「ワイド団信」の利用も検討しましょう。保険料は高くなりますが、審査のハードルは比較的低くなります。
60代におすすめの住宅購入方法3選
60代で住宅を購入する場合、通常の住宅ローン以外にも選択肢があります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
リバースモーゲージ型住宅ローン
リバースモーゲージ型住宅ローンは、60歳以上を対象にした「自宅の資産価値を活かして資金を借りるサービス」です。最大の特徴は「毎月の支払いは利息のみ」という点で、元金の返済は契約者の死亡時に行います。
メリット:
- 毎月の返済負担が利息分のみで軽い
- 資金使途が比較的自由(住宅購入だけでなくリフォームや借り換えも可能)
- 60歳以上であれば年齢上限がなく、70代、80代でも利用可能な場合がある
- 老後資金と住宅取得を両立できる
デメリット:
- 対象エリアが首都圏や関西圏など主要都市に限られていることが多い
- 担保評価が定期的に見直され、価値下落時にリスクがある
- 変動金利型が多く、将来金利上昇の可能性がある
- 年利2~4%程度と通常の住宅ローンより金利が高め
リバースモーゲージには「リコース型」と「ノンリコース型」の2種類があります。リコース型は契約者死亡時に相続人が残債を返済する必要があり、ノンリコース型は物件の売却で返済が完了します(不足分は金融機関が負担)。フラット35のデータでは、2019年度の申込者の約98%がノンリコース型を選択しています。
りそな銀行の「あんしん革命」などでは50歳から申し込み可能で、物件の購入やサービス付き高齢者向け住宅の入居一時金などにも利用できます。
リースバック
リースバックとは、所有している自宅を不動産会社などに売却し、その後賃貸住宅として借りることで、現金を手に入れながらも同じ家に住み続けられる仕組みです。
メリット:
- まとまった資金を一度に手に入れられる
- 住み慣れた家に継続して居住できる
- 資産運用の柔軟性が高まる
- 相続税対策になる場合もある
デメリット:
- これまで持ち家だった人は新たに家賃の支払いが発生する
- 自宅の所有権が運営会社に移る
- 賃料は「売却価格×期待利回り÷12カ月」で算出され、期待利回りは6~14%程度と幅がある
- 多くは定期借家契約のため、更新時に貸主が更新を拒否するリスクがある
リースバックは、まとまった現金が必要な場合や、住宅ローンの残債が残っている物件を手放す必要がある場合に検討する価値があります。ただし、毎月の家賃支払いが新たな負担となるため、長期的な資金計画をしっかり立てる必要があります。
親子リレーローン
親子リレーローンは、親と子の2世代にわたってリレー形式で返済する住宅ローンです。親が返済できなくなった場合や亡くなった場合に、子が返済を引き継ぐ仕組みになっています。
メリット:
- 返済期間を長く設定できるため、月々の返済額を抑えられる
- 親が高齢でも住宅ローンを組みやすくなる
- 将来的に子どもが住む予定の家であれば、スムーズな継承が可能
- 親の生前に住宅資産を効率的に移転できる場合もある
デメリット:
- 団信に親子のどちらか一方しか加入できない場合が多い
- 子に返済義務が移るため、子の同意と協力が不可欠
- 子の将来の経済状況によっては負担になる可能性がある
- 子の住宅ローン控除が受けられない場合がある
親子リレーローンを検討する際は、親と子双方で十分に話し合い、将来的なライフプランを共有することが重要です。特に子が別途住宅購入を考えている場合は、返済負担が二重になる可能性もあるため注意が必要です。
60代からの住宅ローン活用術
実際に60代で住宅ローンを活用した方々の例を見ていきましょう。成功例から学ぶことで、自分自身の住宅購入計画に活かせるポイントが見えてきます。
事例1:退職金と頭金を組み合わせた賢い借り入れ
Aさん(62歳・会社員)のケース:
- 購入物件:都内マンション 4,000万円
- 退職金予定:2,000万円
- 自己資金:1,000万円
- 住宅ローン:1,000万円(返済期間15年)
- 月々の返済額:約6万円
Aさんは、定年退職を2年後に控えていましたが、都心のマンションへの住み替えを希望していました。退職金と貯蓄を合わせて3,000万円を頭金とし、残りの1,000万円を住宅ローンで借り入れる計画を立てました。
金融機関との交渉では、退職後も継続雇用が決まっていることと、安定した年金収入が見込めること、また借入額が物件価格の25%程度と少額であることをアピール。結果的に審査に通り、希望のマンションを購入することができました。
Aさんの成功ポイントは、「無理のない借入額」と「将来の収入見込みを明確に示せたこと」です。退職金を上手く活用しつつ、老後資金も確保したバランスの良い計画が評価されました。
事例2:リバースモーゲージを活用した住み替え
Bさん夫妻(65歳・年金生活者)のケース:
- 購入物件:郊外の平屋住宅 3,500万円
- 自己資金:1,500万円
- リバースモーゲージ:2,000万円
- 月々の支払い:利息のみ(約3万3,000円)
Bさん夫妻は、郊外の平屋住宅へ住み替えを検討していました。バリアフリー設計の住居で老後を過ごしたいという希望がありましたが、自己資金だけでは足りませんでした。
そこでリバースモーゲージ型住宅ローンを検討。毎月の支払いが利息のみであること、元金返済が不要なことから、年金生活でも無理なく返済できると判断しました。また、子どもたちとも話し合い、将来的には物件を売却して返済することに合意していました。
Bさん夫妻の成功ポイントは、「家族との事前合意」と「リバースモーゲージの特性を活かした計画」です。月々の負担を最小限に抑えながら理想の住まいを手に入れることができました。
事例3:親子リレーローンで二世帯住宅を建設
Cさん(67歳)とその息子(42歳)のケース:
- 購入物件:二世帯住宅 5,500万円
- 自己資金:1,500万円
- 親子リレーローン:4,000万円(返済期間30年)
- 月々の返済額:約14万円(当初はCさんが負担、後に息子が引き継ぎ)
Cさんは息子家族と同居するため、二世帯住宅の建設を計画していました。しかし、67歳という年齢では通常の住宅ローンを組むことが難しいケースでした。
そこで親子リレーローンを活用。Cさんには安定した年金収入があり、息子も正社員として安定した収入を得ていたことから、親子合算での審査を申請しました。息子が将来的にローンを引き継ぐことを前提に、30年という長期の返済期間を設定することができました。
Cさんのケースの成功ポイントは、「将来の居住者である子も含めた計画」と「親子での協力体制の構築」です。両者のライフプランを擦り合わせ、親子で話し合いながら進めたことが成功の鍵となりました。
重要なポイント:各事例から学ぶこと
これらの事例から共通して見えてくるのは、以下の重要なポイントです:
- 無理のない資金計画:収入と支出のバランスを考えた計画が重要
- 将来を見据えた判断:老後の生活変化も視野に入れた計画
- 家族との合意形成:特に相続や共同で返済する場合は事前の話し合いが不可欠
- 適切な住宅ローン商品の選択:自分の状況に最適な住宅ローン商品を検討
- 複数の選択肢を比較検討:一つの方法にこだわらず、様々な可能性を探る
60代からの住宅購入は、若い世代とは異なる視点が必要です。これらのポイントを踏まえながら、自分に最適な住宅購入プランを考えることが大切です。
まとめ:60代でもマイホームを諦めないための戦略
この記事では、60代で住宅ローンの審査に通らない理由と、その対策について詳しく解説してきました。最後に、60代からでもマイホームを手に入れるための戦略をまとめておきましょう。
60代での住宅ローン審査が厳しい主な理由
- 収入の安定性と継続性に疑問符がつく
- 年齢制限に引っかかりやすい
- 健康状態と団体信用生命保険の壁
- 担保評価に厳しい目が向けられる
- 老後資金との兼ね合いが懸念される
60代で住宅ローン審査に通るための対策
- 頭金を増やして借入額を減らす
- 担保評価の高い物件を選ぶ
- 複数の金融機関に申し込む
- 安定した収入源を確保・証明する
- 健康状態をアピールする
60代におすすめの住宅購入方法
- リバースモーゲージ型住宅ローン
- リースバック
- 親子リレーローン
60代での住宅購入は、単に「家を買う」という以上に、老後の生活全体を見据えた計画が必要です。住宅ローンの返済だけでなく、固定資産税や修繕費などの維持費用、将来的な医療・介護費用も考慮して、総合的な資金計画を立てることが重要です。
また、「住宅を持つ」ことだけが選択肢ではないことも忘れてはいけません。賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅など、自分のライフスタイルや健康状態に合わせた選択肢も検討する価値があります。
最終的には、「これからの人生をどう生きたいか」というビジョンを明確にした上で、それを実現するための住まい方を選ぶことが大切です。金融機関や不動産会社だけでなく、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しながら、自分に最適な住まい選びを進めましょう。
60代だからこそ、人生経験を活かした賢い選択ができるはずです。この記事が、あなたの理想の住まいを見つける一助になれば幸いです。
