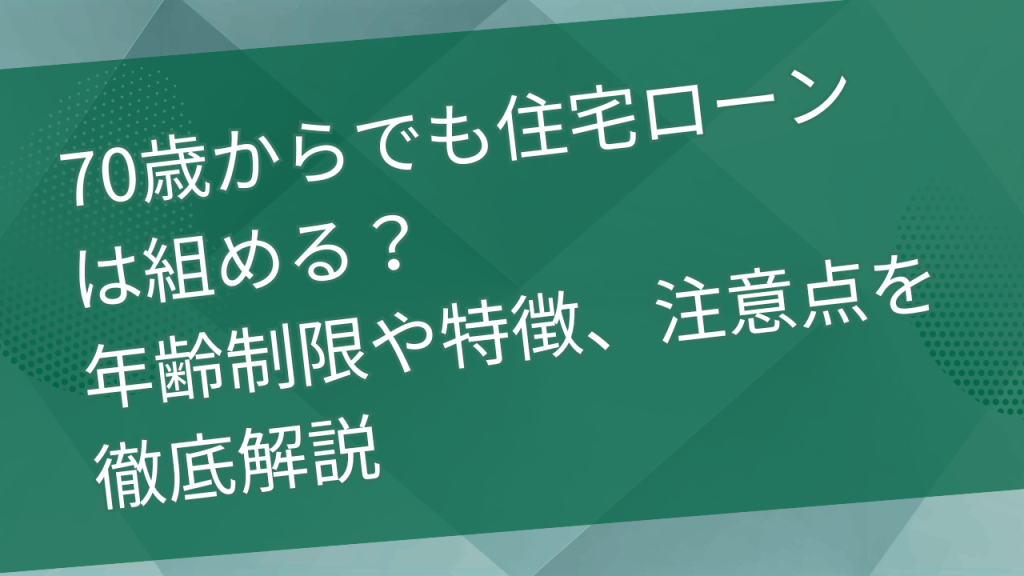
「70歳を過ぎてからマイホームを購入することは可能なのか」「住宅ローンは組めるのか」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、70歳からでも住宅ローンを組むことは可能です。しかし、年齢による制限や条件があり、通常よりも注意すべき点がいくつかあります。
この記事では、70歳からの住宅ローン利用について詳しく解説します。高齢者向けの住宅ローン事情から金融機関ごとの年齢制限、実際のシミュレーション例、そして住宅ローン以外の選択肢まで網羅的にお伝えします。
「第二の人生」を満喫するためのマイホーム取得を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
住宅ローンを簡単に比較してあなたにぴったりの金利の安い銀行が探せる!
モゲチェックだけの優遇金利でお得に借りよう!
↓↓↓↓↓
目次
なぜ70歳からマイホームを検討する人が増えているのか
「マイホーム購入」というと、結婚や出産を機に検討することが多いイメージがありますよね。実際、多くの方は30代から40代でマイホームを購入しています。
しかし近年、70代でマイホーム購入を検討するシニア層が増加しています。その背景には以下のような理由があります。
ライフスタイルの変化
子どもが独立して夫婦二人の生活になったことをきっかけに、「今の住まいは広すぎる」「管理が大変」といった理由から、コンパクトな住まいへの住み替えを検討する方が増えています。
また、長年賃貸で暮らしてきた方が、「老後は自分たちの家で過ごしたい」と考えてマイホーム購入を決意するケースも少なくありません。
定年退職後の住まい
「定年退職後、故郷に戻って家を建てたい」「趣味を楽しめる理想の住まいで第二の人生を過ごしたい」という願望を持つ方も多いです。
仕事のための通勤や子育ての便利さを重視する必要がなくなり、ようやく自分たちの理想の住まいや住みたい場所を選べる自由を手に入れた、という方も少なくないでしょう。
平均寿命の延びと健康寿命の向上
日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性が87.57歳(2021年時点)と世界有数の長寿国です。健康寿命も延びており、70代でも元気に活動できる方が増えています。
「まだまだ長い人生が残っている」という前向きな考えから、70歳を過ぎてからでも住環境の改善を図りたいと考える方が増えているのです。
とはいえ、マイホーム購入には多額の資金が必要です。70歳からでも住宅ローンを利用することは可能なのでしょうか?
70歳からでも住宅ローンを組めるのか
結論から言うと、70歳からでも住宅ローンを組むことは可能です。ただし、いくつかの条件や制限があります。
住宅ローンの年齢制限の基本
住宅ローンには主に以下の2つの年齢制限があります。
- 借入時年齢:ローンを組む時点での年齢の上限
- 完済時年齢:ローンを完済する予定の年齢の上限
かつては住宅ローンの借入時年齢の上限は65歳未満が一般的でしたが、平均寿命の延びや定年退職年齢の上昇に伴い、現在では多くの金融機関が借入時年齢の上限を70歳前後まで引き上げています。
完済時年齢については、多くの金融機関で80歳前後が上限となっています。
そのため、70歳で住宅ローンを組む場合、80歳までの10年間で完済する計画を立てる必要があります。
金融機関別の年齢条件比較
主要な金融機関における借入時年齢と完済時年齢の上限をまとめました。
| 金融機関名 | 借入時年齢の上限 | 完済時年齢の上限 |
|---|---|---|
| みずほ銀行 | 満71歳未満 | 満81歳未満 |
| 三菱UFJ銀行 | 70歳の誕生日まで | 80歳の誕生日まで |
| 三井住友銀行 | 満70歳の誕生日まで | 満80歳の誕生日 |
| りそな銀行 | 満70歳未満 | 満80歳未満 |
| 三井住友信託銀行 | 満71歳未満 | 満81歳未満 |
| イオン銀行 | 満71歳未満 | 満80歳未満 |
| フラット35 | 70歳未満 | 80歳 |
| ARUHI | 満70歳未満 | 満80歳未満 |
| 住信SBIネット銀行 | 満65歳以下 | 満80歳未満 |
| auじぶん銀行 | 満65歳未満 | 80歳の誕生日まで |
| ソニー銀行 | 満65歳未満 | 満85歳未満 |
※2023年~2025年時点での情報です。最新情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
表を見るとわかるように、借入時年齢の上限は金融機関によって微妙に異なります。「満70歳未満」と「70歳の誕生日まで」では厳密には意味が異なりますので、申し込みを検討する際には細かい条件を確認することが重要です。
また、完済時年齢については、ほとんどの金融機関が80歳前後を上限としていますが、ソニー銀行のように85歳まで引き上げている金融機関もあります。これは晩婚化や住宅価格の上昇による返済期間の長期化などの社会情勢に対応したものです。
ただし、注意しておきたいのは、規定上の年齢条件を満たしていても、必ずしも住宅ローンが組めるとは限らないということです。特に年齢の上限ギリギリでの申し込みの場合、金融機関は審査をより慎重に行う傾向があります。
70歳からの住宅ローンシミュレーション
70歳で住宅ローンを組む場合、多くの金融機関では完済時年齢が80歳までとなっているため、最長でも10年の返済期間となります。返済期間が短いと、同じ借入額でも月々の返済負担が大きくなる点に注意が必要です。
【ケース】70歳から住宅ローンを組むケース
ここでは、70歳のAさんが住宅ローンを検討するケースをシミュレーションしてみましょう。
Aさんのプロフィール:
- 70歳、退職後も継続雇用で月給18万円(年収約300万円)
- 退職金500万円を頭金として用意
- 2,000万円の中古マンションの購入を検討
- 借入希望額:1,500万円
この場合、完済時年齢の上限が80歳であれば、最長10年のローンを組むことになります。
借入額1,500万円、返済期間10年、金利1.5%(固定金利型)の場合の毎月の返済額は約13.5万円となります。
年収300万円に対して毎月の返済額が13.5万円というのは、返済負担率が約54%となり、通常の安全基準(年収に対して返済額が25%以下)を大きく上回ります。
このケースでは、住宅ローンの審査に通るのは非常に厳しいでしょう。
では、同じ条件で借入可能額を返済負担率25%に抑えた場合、いくらまで借りられるでしょうか。
年収300万円の25%は年間75万円。月々の返済額は約6.25万円が上限となります。金利1.5%、10年返済で計算すると、借入可能額は約700万円となります。
つまり、1,500万円の物件を購入するためには、頭金として800万円以上必要になるということです。
返済負担率と借入可能額の関係
以下のシミュレーションは、年収別・返済負担率別の借入可能額の目安です。(借入期間10年、金利1.5%、元利均等返済、ボーナス払いなしの場合)
年収300万円の場合
| 返済負担率 | 毎月の返済額 | 借入可能額 | 総支払額(元本+利息) |
|---|---|---|---|
| 20% | 約5万円 | 約560万円 | 約600万円 |
| 25% | 約6.25万円 | 約700万円 | 約750万円 |
| 30% | 約7.5万円 | 約840万円 | 約900万円 |
年収400万円の場合
| 返済負担率 | 毎月の返済額 | 借入可能額 | 総支払額(元本+利息) |
|---|---|---|---|
| 20% | 約6.67万円 | 約748万円 | 約800万円 |
| 25% | 約8.33万円 | 約935万円 | 約1,000万円 |
| 30% | 約10万円 | 約1,122万円 | 約1,200万円 |
年収500万円の場合
| 返済負担率 | 毎月の返済額 | 借入可能額 | 総支払額(元本+利息) |
|---|---|---|---|
| 20% | 約8.33万円 | 約935万円 | 約1,000万円 |
| 25% | 約10.42万円 | 約1,169万円 | 約1,250万円 |
| 30% | 約12.5万円 | 約1,403万円 | 約1,500万円 |
一般的に返済負担率は20~25%以下に抑えることが推奨されています。特に高齢者の場合は、予期せぬ医療費や介護費用が発生するリスクもあるため、返済余力を十分に確保しておくことが重要です。
また、70歳からの住宅ローンは返済期間が短いため、同じ金額を借りるなら若い世代より毎月の返済額が大きくなります。返済計画は十分な余裕を持って立てるようにしましょう。
「この年収だとどのくらいの物件が買えるんだろう?」と考えている方は、事前に住宅ローンの借入可能額を計算してみることをおすすめします。銀行の窓口やモーゲージプランナーなどに相談すれば、より詳細なシミュレーションを無料で行ってくれる場合もあります。
住宅ローン以外の選択肢
70歳を超えると、通常の住宅ローンを組むことが難しい場合やあまり得策でない場合もあります。ここでは、住宅ローン以外で住宅を確保する方法をご紹介します。
リバースモーゲージ型住宅ローン
リバースモーゲージ型住宅ローンは、自宅を担保にして融資を受ける高齢者向けの金融商品です。通常の住宅ローンとは異なり、契約者の存命中は利息のみを返済し、死亡後に自宅を売却して元本を返済する仕組みです。
リバースモーゲージ型住宅ローンのメリット
- 生存中は利息の支払いのみなので、毎月の返済負担が軽い
- 年金収入だけの高齢者でも利用しやすい
- 通常の住宅ローンよりも審査基準が柔軟な場合がある
- ノンリコース型であれば、不動産価値が下落しても相続人の追加支払いが不要
リバースモーゲージ型住宅ローンのデメリット
- 融資額は自宅の評価額の50~65%程度までで、上限が設けられていることが多い
- 通常の住宅ローンよりも金利が高い傾向がある
- 長生きするほど利息の支払い総額が大きくなる
- 団体信用生命保険(団信)に加入できないケースが多い
- 物件に制限があり、戸建て住宅が主な対象(土地部分が担保評価されるため)
リバースモーゲージ型住宅ローンには「リコース型」と「ノンリコース型」の2種類があります。
リコース型は、契約者の死亡後に自宅を売却しても借入元本に届かない場合、相続人が残りの返済義務を負います。
ノンリコース型は、自宅の売却価格が借入金額を下回っても、相続人に返済義務がなく、担保物件の売却で清算されます。ただし、ノンリコース型は金利が高く設定される傾向があります。
「老後の住まいを確保したいけれど、毎月の返済負担は最小限に抑えたい」という方には、リバースモーゲージ型住宅ローンも検討の価値があるでしょう。
リ・バース60
「リ・バース60」は住宅金融支援機構が提供する、満60歳以上の方を対象とした住宅ローン商品です。基本的な仕組みはリバースモーゲージ型住宅ローンと同じですが、使途が住宅関連(住宅の建設、購入、リフォーム、住宅ローン借り換えなど)に限定されています。
融資限度額は以下の通りです。
- 60歳以上:担保となる不動産の評価額の50~65%(ただし8,000万円以下)
- 50~60歳未満:担保となる不動産の評価額の30%(ただし8,000万円以下)
リ・バース60のメリットとしては、住宅金融支援機構が提供する商品なので比較的安心感があること、生存中は利息のみの返済で済むこと、高齢でも融資を受けられる可能性が高いことなどが挙げられます。
一方、デメリットとしては、融資額に上限があること、長生きするほど総支払額が増えること、完済するまで返済が続くため、相続を考える場合は計画的な準備が必要なことなどがあります。
リースバック型住宅ローン(住宅売却・賃貸借方式)
リースバックは、自分の所有する自宅を業者に売却し、そのまま賃貸借契約を結んで住み続ける方法です。住宅ローンではありませんが、住まいを確保しながらまとまった資金を得る手段として利用されています。
リースバックのメリット
- 自宅を売却することでまとまった資金を手に入れられる
- 住み慣れた家に住み続けることができる
- 物件の管理費や固定資産税の負担から解放される
- 引っ越しの手間や費用がかからない
- 近隣に売却を知られるリスクが少ない
リースバックのデメリット
- 売却価格が市場相場より低くなることが多い
- 月々の賃料が周辺相場より高く設定される場合がある
- 賃貸借契約の更新時に断られる可能性もある
- 子どもや配偶者に資産として残すことができなくなる
リースバックは年齢制限なく利用できるため、70歳を超えても検討できる選択肢です。「まとまった資金が必要だけど、住み慣れた家から離れたくない」という方に適した方法かもしれません。
ただし、リースバックは比較的新しいサービスで、業者によって条件が大きく異なります。契約内容をしっかり確認し、法律の専門家などにも相談した上で判断することをおすすめします。
終身建物賃貸借
最後にご紹介するのは「終身建物賃貸借」という賃貸契約です。これは住宅を購入する方法ではありませんが、高齢者が安心して住める住まいを確保する選択肢の一つです。
終身建物賃貸借は、60歳以上の高齢者を対象とした契約形態で、死亡するまで住み続けることを前提に家を借りる制度です。通常の賃貸契約とは違い、貸主からの更新拒否や解約の申し入れができないため、終の棲家として安心して住み続けることができます。
終身建物賃貸借のメリット
- 更新料が不要
- 住宅はバリアフリー基準を満たした物件
- 契約者が死亡した後も同居していた配偶者などが住み続けることができる
- 住宅購入に比べて初期費用が少なくて済む
終身建物賃貸借のデメリット
- 国土交通省の認可を受けている物件がまだ少ない
- 60歳以上の高齢者と配偶者、親族しか入居できない
- 資産形成にはならない
一般的に、高齢になるほど賃貸契約を結ぶことは難しくなる傾向がありますが、終身建物賃貸借なら高齢者でも安心して賃貸契約を結ぶことができます。
「マイホームを持ちたいが資金面で難しい」「賃貸でも良いから安心して住める住まいが欲しい」という方は、終身建物賃貸借も選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
高齢者が住宅ローンを利用する際の注意点
70歳で住宅ローンを組む場合、一般的な住宅ローンとは異なる注意点がいくつかあります。ここでは、高齢者が住宅ローンを利用する際に特に注意すべきポイントをご紹介します。
住宅ローン審査のポイント
高齢者の住宅ローン審査では、以下の要素が特に重視されます。
健康状態
多くの住宅ローンでは、団体信用生命保険(団信)への加入が条件となっています。団信は、ローン契約者が死亡した場合に保険金でローン残高を返済してくれる保険です。
高齢になるほど健康上のリスクが高まるため、健康状態によっては団信に加入できず、住宅ローンの契約ができない場合があります。申し込み前に健康診断を受けるなどして、健康状態を把握しておくことが大切です。
なお、団信加入が任意となっているフラット35などの商品もあります。健康上の理由で団信に加入できない場合は、このような商品を検討するのも一つの方法です。
収入の安定性
住宅ローンの審査では、安定した収入があるかどうかも重要な判断材料となります。70歳であれば多くの方が退職されていますが、年金収入や不動産収入、継続的な雇用収入などが安定的にあることが求められます。
特に年金収入のみの場合は、年金額と返済額のバランスがしっかりと取れているか厳しくチェックされます。年金額が少ない場合は、借入可能額も制限されることになります。
資産状況
高齢者の場合、収入に加えて保有資産も審査の重要なポイントとなります。預貯金や有価証券などの金融資産、他の不動産所有など、総合的な資産状況が審査されます。
十分な自己資金を用意できれば、借入額を減らすことができ、結果的に審査が通りやすくなる可能性があります。特に退職金を住宅購入資金に充てる場合は、生活資金とのバランスを考えて計画することが大切です。
物件の担保価値
高齢者のローン審査では、購入する物件の資産価値や将来的な売却のしやすさも重視されます。例えば、駅から遠い場所や過疎地域の物件、築年数の古い物件などは、将来的な資産価値の下落リスクが考慮され、審査が厳しくなる場合があります。
また、高齢者が住みやすいバリアフリー設計の物件や、都市部の利便性の高い物件など、将来的な需要が見込める物件の方が審査で有利になることもあります。
生活資金の確保
70歳からマイホームを購入する場合、住宅ローンの返済だけでなく、老後の生活資金も十分に確保しておくことが重要です。
日本人の平均寿命を考えると、70歳の方でも10年以上の生活設計が必要です。その間には、日常生活費だけでなく、医療費や介護費用の増加も見込まれます。さらに、住宅を所有すれば修繕費や管理費、固定資産税などの費用も継続的に発生します。
たとえ返済負担率が低くても、老後の生活資金が十分に確保できない場合は、マイホーム購入を見送ることも選択肢の一つです。無理な住宅ローンを組んで、後から生活が苦しくなっては本末転倒ですよね。
以下のような費用も考慮して、総合的に資金計画を立てましょう:
- 日常の生活費(食費、光熱費、通信費など)
- 医療費・介護費(特に高齢になるほど増加する傾向あり)
- 住宅の修繕費・管理費(10年以内でも突発的な修繕が必要になることも)
- 固定資産税などの税金
- 趣味や旅行などの娯楽費(充実した老後生活のため)
できれば、住宅ローンの返済額以外にも、月々の出費や将来的な臨時出費に対応できる余裕資金を確保しておくことをおすすめします。
相続や売却の計画
70歳でマイホームを購入する場合、将来的な相続や売却についても事前に計画しておくことが重要です。
相続対策
住宅を購入した後、万が一のことがあった場合を想定して、相続についても考えておくことが大切です。特に住宅ローンが残っている状態で相続が発生した場合は、相続人が住宅とローンの両方を相続することになります。
相続人が住宅に住む意向がない場合や、ローンの返済が難しい場合などは、スムーズに売却できるような対策を考えておく必要があります。事前に家族と話し合い、遺言書を作成しておくことも一つの方法です。
売却計画
将来的に介護施設への入居が必要になった場合など、住宅を売却する可能性も考慮しておきましょう。住宅の購入時から「将来売却することを想定して」物件を選ぶと良いでしょう。
例えば、駅から近い、周辺環境が良い、間取りが一般的で使いやすいなど、将来的に売却しやすい物件を選ぶことがポイントです。また、定期的なメンテナンスを行い、物件の価値を維持することも大切です。
認知症対策
高齢になるにつれて認知症のリスクも高まります。認知症になると自分で不動産の売却手続きなどを行うことができなくなる可能性があります。
そのような場合に備えて、家族信託や任意後見契約など、事前に対策を講じておくことも検討すべきでしょう。特に子どもがいない場合や、頼れる親族が近くにいない場合は、専門家に相談して対策を立てておくことをおすすめします。
親子リレー返済制度の活用
完済時年齢の上限を超えてしまうような場合でも、「親子リレー返済制度」を利用できる可能性があります。
親子リレー返済とは、親子で1つの住宅ローン契約を結び、親が返済を開始し、年齢上限に達したら子に返済を引き継ぐ仕組みです。この制度を利用すれば、70歳を超えても住宅ローンを組める可能性があります。
親子リレー返済の場合、審査では引き継ぐ子の年齢と親子全体の収入をもとに判断されます。ただし、この制度を利用するためには、子どもも連帯債務者や連帯保証人になる必要があるため、子どもの協力が不可欠です。
また、金融機関によって親子リレー返済の取り扱いが異なりますので、利用を検討する場合は、事前に各金融機関に確認することをおすすめします。
「子どもと一緒に住む予定がある」「子どもが近くに住んでいて、将来的に同居する可能性がある」といった場合は、親子リレー返済も有効な選択肢の一つとなるでしょう。
まとめ:70歳からのマイホーム購入は計画的に
70歳からでも住宅ローンを組むことは不可能ではありませんが、借入時年齢と完済時年齢の条件、返済計画、生活資金の確保など、さまざまな要素を慎重に検討する必要があります。
この記事でご紹介した内容をまとめると:
- 住宅ローンの年齢条件:多くの金融機関で借入時年齢の上限が70歳前後、完済時年齢の上限が80歳前後と設定されています。
- 返済計画:返済期間が10年程度と短くなるため、毎月の返済負担が大きくなります。余裕を持った資金計画が必要です。
- 審査のポイント:高齢者の住宅ローン審査では、健康状態、収入の安定性、資産状況、物件の担保価値などが重視されます。
- 生活資金の確保:住宅ローンの返済だけでなく、医療費や介護費用なども見据えた生活資金の確保が重要です。
- 相続・売却の計画:将来的な相続や売却も視野に入れた計画を立てましょう。
- 住宅ローン以外の選択肢:リバースモーゲージ型住宅ローン、リ・バース60、リースバック、終身建物賃貸借なども検討の価値があります。
70歳からのマイホーム購入は、「老後の住まい」という視点だけでなく、「資産としての価値」「将来の相続」「生活の質」など、多角的な視点から検討することが大切です。
特に重要なのは、無理のない返済計画と十分な老後資金の確保です。住宅ローンの返済に追われて老後生活が苦しくなってしまっては本末転倒ですよね。
金融機関や住宅販売会社の営業担当者だけでなく、ファイナンシャルプランナーなどの中立的な立場の専門家にも相談しながら、慎重に判断することをおすすめします。
また、家族との話し合いも重要です。将来的な相続や介護の問題も含めて、家族全員が納得できる計画を立てることが、安心してマイホームを購入するポイントになります。
人生100年時代と言われる今、70歳はまだまだ元気に活動できる年齢です。ライフスタイルに合った住まいで充実した老後を過ごすために、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。
最後に、住宅ローンを検討される際は、必ず最新の情報を各金融機関の公式サイトや窓口で確認するようにしてください。金利や条件は随時変更される可能性があります。
充実した第二の人生のための住まい選び、応援しています!
